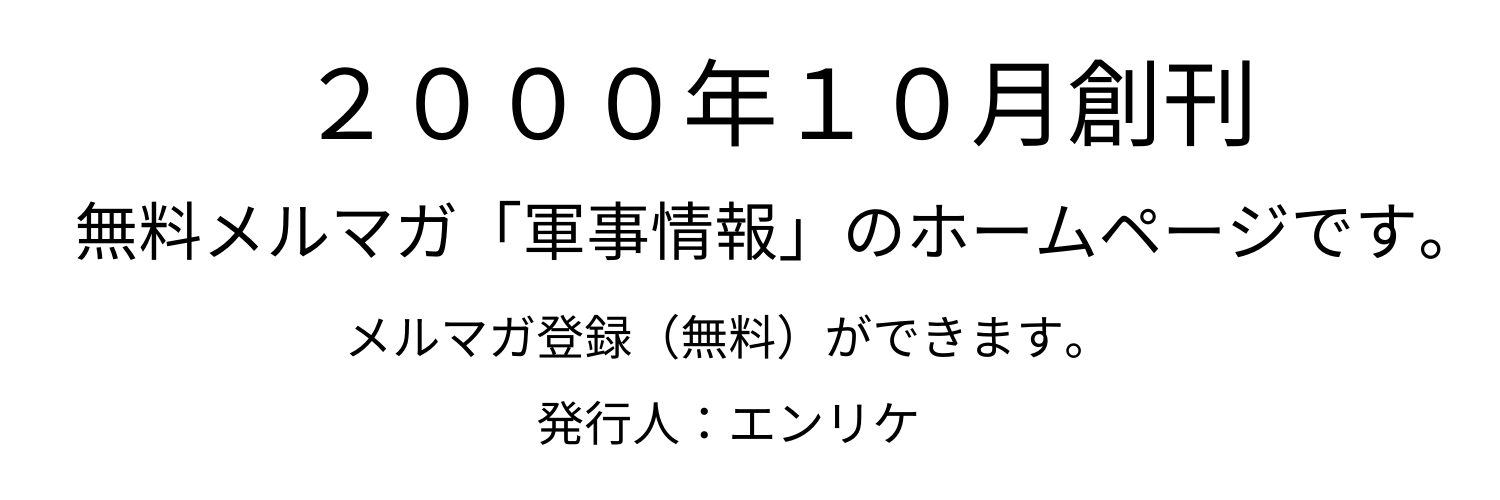武士道精神の実践:剣と外国人ーー武士道精神入門(20)
{{Information |Description= 高野佐三郎 |Source= 『月刊剣道日本』1984年12月号 |Date= 1945年以前 |Author= 不明 |Permission= {{PD-old-USJP}} }}▽ ごあいさつ
こんにちは。日本兵法研究会会長の家村です。
今回は「武士道精神の実践」の第六話といたしまして、「剣と外国人」を紹介いたします。
これまで、日本人が長い歴史を通じて培い、磨き上げ、守り続けてきた価値観や伝統精神である『武士道精神』について皆様とともに学んでまいりましたが、この武士道精神は日本人以外の人、つまり外国で生まれ育った人たちにも通じるものなのでしょうか。そんな疑問もあり、昭和初期の雑誌から見つけ出した大変興味深い記事を要約(現代語訳)して紹介いたします。
それでは、本題に入ります
【第20回】武士道精神の実践:剣と外国人
▽ 精神を統一せぬかぎり勝負は負ける
「昭和の剣聖」と呼ばれた高野佐三郎氏は、文久2(1862)年に武蔵国秩父郡(現埼玉県秩父市)に生まれ、幼少から祖父で忍(おし)藩指南役の高野佐吉郎に剣術を学び、成人する頃には上京して山岡鉄舟の門弟となった。
明治19(1886)年に二十四歳で警視庁巡査に任官し、二年後には埼玉県警察本部武術教授(警部)となる。その後、明信館道場(のち修道学院)を設立して多くの剣道家を輩出するとともに、東京高等師範学校や早稲田大学で教えながら、剣道の指導者養成や、学校での剣道指導法の考案、形の制定・普及など近代剣道の完成に尽力した。
「剣の道は深い」、「精神を統一せぬかぎり勝負は負ける」といった格言も遺している。
このように、大正から昭和初期の剣道界の第一人者であった高野佐三郎氏が、昭和10(1935)年に雑誌「武道」で剣道を学ぶ外国人について話しておられる。
▽ いろいろな国民性と剣道
この記事の冒頭、次のようなことが書いてあるが、今も変わらぬ国民性がにじみ出ていて非常に興味深い。
― 私は昔から、いろいろの外国人に、剣道を教えてきましたが、中でも一番、ものにならぬのは、支那人であります。元来、器用な国民ですから、技術はできないでもないが、精神的に全然駄目なのであります。加減して稽古をつけている時は、直ぐ得意になってしまうが、少し真剣な稽古となると、もう道場の隅(すみ)に逃げて行って、怯(おび)えているという有様です。
「相手が弱ければ起つ。強ければ、逃げるよりほかに仕方がない。」この心持が、彼らから離れることがない。およそ剣道の修業には、縁のない精神であります。
そこへゆくと、ドイツ人は元来、尚武の気風の盛ん国民だけに、支那人などとは比較にならぬ程、積極果敢な気性に富んでおります。
ロシア人なども、一見頗(すこぶ)る鈍重で、技術は下手でありますが、非常に粘り強く、随分(ずいぶん)負けん気があって、頑張りが続きます。こういう国民が精紳を打込んで、本当に剣道を会得したならば、相当恐るべきものがあろうと思はれます、云々 ―
▽ 英国軍人ミッチェル大尉の入門
明治43(1910)年の春、英国大使館附武官のミッチェル大尉が、高野氏の道場へ入門を願い出た。高野氏は答えた。
「私はこれまでにも、多くの外国人に剣道を教えてみました。が、ものになったという人はまだ一人もないのです。おそらく努力や修業の如何(いかん)というよりも、剣道の建前からして、その精神を学ぶことは、あなた方のような外国の人々にとって、不可能のことではなかろうかと思います。やるとなれば、ずいぶん苦しい修業もしなければならないのであるから、今一度よくお考えになってはどうですか。・・・」
しかし、それでもミッチェル大尉は、熱心に入門を希望した。そこまで言うのであれば、と道場に連れて行き、高野氏が簡単な稽古をつけた。面を二つ三つばかりお見舞いすると、ミッチェル大尉は声をたて、うずくまってしまった。
「今日ハ、コレデ十分デス。頭ガ大変イタイデス。失礼シマス。」そう言ったきり、帰ってしまった。
▽ 少年剣士に学ぶ「武人の心意気」
これに懲(こ)りたと思いきや、さにあらず。ミッチェル大尉は、翌日から高野氏の道場に通いはじめて、一年間、欠席なしに、しかも一心不乱に習い続けた。
そこで、高野氏も見込みありと思うと、本格的に修業を始めた。ビシビシと打込んで行くと、ミッチェル大尉の肘(ひじ)がたちまち紫色に腫(は)れあがり、足の皮はすりむけて血がにじみだした。呻(うめ)き声をあげて、頑張っていたミッチェル大尉も、とうとうその翌日から姿を見せなくなった。
今まで無欠席だったのが、休んでしまって音沙汰も無く、・・・そして一週間ほどすると、また出てきた。
「カラダガ痛ンデ、タマラナイ。足ニハ血マメ、イクツモデキマシタノデ、熱海ヘ治療ニ行ッテイマシタ。」
そう言っているところへ、一人の少年弟子が高野氏の前へきた。小さな両足に、大きな血まめを幾つもこしらえている。ちようど好い機会だ、と思った高野氏は、その少年の血まめを、ミッチェル大尉の前で治療して見せた。
火箸(ひばし)の先っぽを真赤に焼いて、足の裏の血まめに押しつける。そのたびに、黄色い煙がブスブスと出る。ジッとこらえてる十二歳の少年、治療が終ると待ちかねていたように、道場へ立って行き、すぐに稽古を始めた。
この始終を、目も放さず見つづけていたミッチェル大尉は、深く感動した顔色をした。これ以来、本格的な修業に精進しつづけて、手足の血まめが破れ、血が流れても、松葉杖をついて道場に通った。そして、ついに実力が二段くらいまで上達した。
▽ 戦場で実証した「不屈の武士的精神」
そこに、第一次世界大戦(欧州大戦)が勃発し、本国からの動員令を受けたミッチェル大尉は、帰国して行った。
フランス戦線において奮戦力闘したミッチェル大尉は、幾度か負傷して入院した。それでも回復するや、すぐに戦場に復帰して祖国の為に戦いつづけた。
その最期には、少数の手兵を率いてドイツ軍の猛撃を抑え、塹壕の中で戦死した。大尉の剣に倒された敵兵の屍骸(しがい)が、かたわらに幾人となく転がり、大尉の血刀は、ボロボロに刃が欠けていた。そして、日本からの帰国に際して高野氏が贈った扇子を、肌身につけていた。
師が弟子との告別に際し、その扇子に書き贈った言葉は、
「一剣留身 應君恩(一剣を身に留めて、大君の恩に応ず)」
であった。
高野氏は、この記事の最後にこう言っておられる。
― 日本武士道を立派に体得して行った、この英国士官は、最後まで退却を頑として受け入れなかったものの様であります。若し彼が、日本の剣道を修めなかったら、あるいは戦死せずにすんだかも知れません。それにしても、外国人の中にも、こういう不屈の武士的精神の持主がいるということは、私どもの深く心にとめなければならぬ所かと思われるのであります。―
(「剣と外国人」終り)
(いえむら・かずゆき)
こんにちは。日本兵法研究会会長の家村です。
今回は「武士道精神の実践」の第六話といたしまして、「剣と外国人」を紹介いたします。
これまで、日本人が長い歴史を通じて培い、磨き上げ、守り続けてきた価値観や伝統精神である『武士道精神』について皆様とともに学んでまいりましたが、この武士道精神は日本人以外の人、つまり外国で生まれ育った人たちにも通じるものなのでしょうか。そんな疑問もあり、昭和初期の雑誌から見つけ出した大変興味深い記事を要約(現代語訳)して紹介いたします。
それでは、本題に入ります
【第20回】武士道精神の実践:剣と外国人
▽ 精神を統一せぬかぎり勝負は負ける
「昭和の剣聖」と呼ばれた高野佐三郎氏は、文久2(1862)年に武蔵国秩父郡(現埼玉県秩父市)に生まれ、幼少から祖父で忍(おし)藩指南役の高野佐吉郎に剣術を学び、成人する頃には上京して山岡鉄舟の門弟となった。
明治19(1886)年に二十四歳で警視庁巡査に任官し、二年後には埼玉県警察本部武術教授(警部)となる。その後、明信館道場(のち修道学院)を設立して多くの剣道家を輩出するとともに、東京高等師範学校や早稲田大学で教えながら、剣道の指導者養成や、学校での剣道指導法の考案、形の制定・普及など近代剣道の完成に尽力した。
「剣の道は深い」、「精神を統一せぬかぎり勝負は負ける」といった格言も遺している。
このように、大正から昭和初期の剣道界の第一人者であった高野佐三郎氏が、昭和10(1935)年に雑誌「武道」で剣道を学ぶ外国人について話しておられる。
▽ いろいろな国民性と剣道
この記事の冒頭、次のようなことが書いてあるが、今も変わらぬ国民性がにじみ出ていて非常に興味深い。
― 私は昔から、いろいろの外国人に、剣道を教えてきましたが、中でも一番、ものにならぬのは、支那人であります。元来、器用な国民ですから、技術はできないでもないが、精神的に全然駄目なのであります。加減して稽古をつけている時は、直ぐ得意になってしまうが、少し真剣な稽古となると、もう道場の隅(すみ)に逃げて行って、怯(おび)えているという有様です。
「相手が弱ければ起つ。強ければ、逃げるよりほかに仕方がない。」この心持が、彼らから離れることがない。およそ剣道の修業には、縁のない精神であります。
そこへゆくと、ドイツ人は元来、尚武の気風の盛ん国民だけに、支那人などとは比較にならぬ程、積極果敢な気性に富んでおります。
ロシア人なども、一見頗(すこぶ)る鈍重で、技術は下手でありますが、非常に粘り強く、随分(ずいぶん)負けん気があって、頑張りが続きます。こういう国民が精紳を打込んで、本当に剣道を会得したならば、相当恐るべきものがあろうと思はれます、云々 ―
▽ 英国軍人ミッチェル大尉の入門
明治43(1910)年の春、英国大使館附武官のミッチェル大尉が、高野氏の道場へ入門を願い出た。高野氏は答えた。
「私はこれまでにも、多くの外国人に剣道を教えてみました。が、ものになったという人はまだ一人もないのです。おそらく努力や修業の如何(いかん)というよりも、剣道の建前からして、その精神を学ぶことは、あなた方のような外国の人々にとって、不可能のことではなかろうかと思います。やるとなれば、ずいぶん苦しい修業もしなければならないのであるから、今一度よくお考えになってはどうですか。・・・」
しかし、それでもミッチェル大尉は、熱心に入門を希望した。そこまで言うのであれば、と道場に連れて行き、高野氏が簡単な稽古をつけた。面を二つ三つばかりお見舞いすると、ミッチェル大尉は声をたて、うずくまってしまった。
「今日ハ、コレデ十分デス。頭ガ大変イタイデス。失礼シマス。」そう言ったきり、帰ってしまった。
▽ 少年剣士に学ぶ「武人の心意気」
これに懲(こ)りたと思いきや、さにあらず。ミッチェル大尉は、翌日から高野氏の道場に通いはじめて、一年間、欠席なしに、しかも一心不乱に習い続けた。
そこで、高野氏も見込みありと思うと、本格的に修業を始めた。ビシビシと打込んで行くと、ミッチェル大尉の肘(ひじ)がたちまち紫色に腫(は)れあがり、足の皮はすりむけて血がにじみだした。呻(うめ)き声をあげて、頑張っていたミッチェル大尉も、とうとうその翌日から姿を見せなくなった。
今まで無欠席だったのが、休んでしまって音沙汰も無く、・・・そして一週間ほどすると、また出てきた。
「カラダガ痛ンデ、タマラナイ。足ニハ血マメ、イクツモデキマシタノデ、熱海ヘ治療ニ行ッテイマシタ。」
そう言っているところへ、一人の少年弟子が高野氏の前へきた。小さな両足に、大きな血まめを幾つもこしらえている。ちようど好い機会だ、と思った高野氏は、その少年の血まめを、ミッチェル大尉の前で治療して見せた。
火箸(ひばし)の先っぽを真赤に焼いて、足の裏の血まめに押しつける。そのたびに、黄色い煙がブスブスと出る。ジッとこらえてる十二歳の少年、治療が終ると待ちかねていたように、道場へ立って行き、すぐに稽古を始めた。
この始終を、目も放さず見つづけていたミッチェル大尉は、深く感動した顔色をした。これ以来、本格的な修業に精進しつづけて、手足の血まめが破れ、血が流れても、松葉杖をついて道場に通った。そして、ついに実力が二段くらいまで上達した。
▽ 戦場で実証した「不屈の武士的精神」
そこに、第一次世界大戦(欧州大戦)が勃発し、本国からの動員令を受けたミッチェル大尉は、帰国して行った。
フランス戦線において奮戦力闘したミッチェル大尉は、幾度か負傷して入院した。それでも回復するや、すぐに戦場に復帰して祖国の為に戦いつづけた。
その最期には、少数の手兵を率いてドイツ軍の猛撃を抑え、塹壕の中で戦死した。大尉の剣に倒された敵兵の屍骸(しがい)が、かたわらに幾人となく転がり、大尉の血刀は、ボロボロに刃が欠けていた。そして、日本からの帰国に際して高野氏が贈った扇子を、肌身につけていた。
師が弟子との告別に際し、その扇子に書き贈った言葉は、
「一剣留身 應君恩(一剣を身に留めて、大君の恩に応ず)」
であった。
高野氏は、この記事の最後にこう言っておられる。
― 日本武士道を立派に体得して行った、この英国士官は、最後まで退却を頑として受け入れなかったものの様であります。若し彼が、日本の剣道を修めなかったら、あるいは戦死せずにすんだかも知れません。それにしても、外国人の中にも、こういう不屈の武士的精神の持主がいるということは、私どもの深く心にとめなければならぬ所かと思われるのであります。―
(「剣と外国人」終り)
(いえむら・かずゆき)