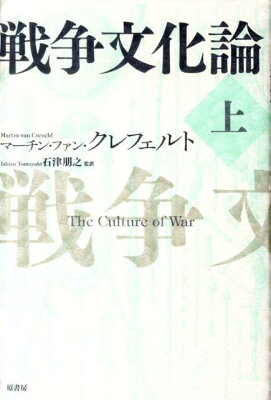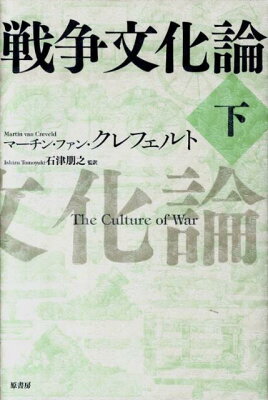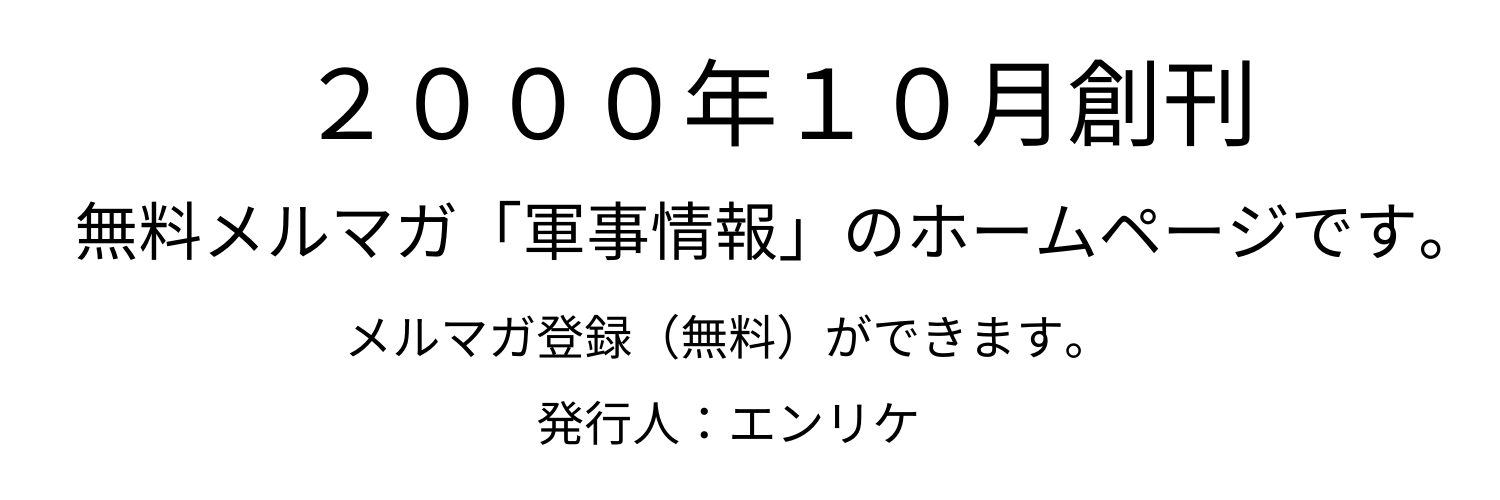「9条もまた戦争文化の一部である」 戦争は人間的な営みである~新戦争文化論~(5) 石川明人
憲法9条?http://xianxian8181.blog73.fc2.com/blog-date-20090509.htmlより
こんにちは。
石川明人(北海道大学助教)です。
前回配信したマガジンへのメッセージをいただきました。
EWAT2672さま。コメントありがとうございます。
ご家族のお話を拝読し、私も厳粛な気持ちになりました。
今でも私の実家には、軍人だった祖父の写真があります。それは戦後に撮ったものなので背広姿ですが、とてもやさしい笑顔です。しかし、戦争中の軍服姿の写真には、緊張と厳しさが感じられます。私はもちろん直接戦争を知らない世代の者ですが、せめて人からよくお話を聞き、よく本を読んで、戦争や軍事について考えてみたいと思います。「平和」というのは、究極的には、平時における私たち一人ひとりの、戦争に関するイマジネーションの力にかかっているのかもしれない、とも思うのです。
べーさま。コメントありがとうございます。
べーさまも似た体験をされたことがあるとのこと、慰められる思いです。学校というのはいろいろな意味で特殊な組織ですね。自衛隊と聞いただけで拒否反応を示す教職員ばかりのところもあれば、逆に、学校単位で自衛隊音楽隊のコンサートを聴きに行くところもあるようです。軍人、あるいは自衛官と、一度でも一緒に御飯を食べたり、お酒を飲んだりすれば、彼らが私たちと全く同じ人間であることを実感できるはずです。多くの人がそれを十分感じていれば、かえって過激で無責任な主戦論なども起きにくくなるでしょう。軍人や自衛官との交流は、非常に大切な平和主義的営みだと思っております。
池田さま。コメントありがとうございます。
別の方への返答にも書きましたが、自衛官の方たちと普通に接する機会があれば、彼らに対する偏見がなくなるのみならず、強気だが無責任な主戦論もなくなると思います。自衛官と知り合いになり、その家族を知っていればなおさら、戦争など起きないといいな、と心から思うものだからです。軍人や自衛官一人ひとりの人格・生活・家族などを想像することそれ自体が、とても大切な「平和主義」的佇まいなのだと考えております。
Yさま。メールをありがとうございました。
ご教示をいただき感謝いたします。吉田茂の有名な言葉は防衛大学校卒業式での訓示ではなく、ある一人の方に直接おっしゃった言葉だったとのこと、初めて知りました。資料も教えていただき、大いに納得いたしました。あらためて、御礼を申し上げます。もし今後もお気づきの点がございましたら、ご指導いただけますよう、何卒よろしくお願い申しあげます。
では、【戦争は人間的な営みである】の第5回目をお送りしましょう。
今回のテーマは、「9条もまた戦争文化の一部である」です。戦争や軍事は、政治、経済、科学技術などと密接なものですが、「平和」について人々の抱く考え方それ自体もまた、広い意味では戦争の一部に他ならないと思われます。
忌憚のないご意見、ご感想をいただければ幸甚に存じます。
(参考動画:石川明人「戦争は人間的な営みである」約15分)
http://www.youtube.com/watch?v=gL_de198QsE
************
私たちの「戦争」イメージ
一般に、戦争について考える、あるいは平和について考える、というと、特に私たち日本人の多くは、無意識のうちに、まず第二次世界大戦のような戦争をイメージして話をする傾向が強いであろう。
特攻隊を送り出し、原爆が落とされ、軍民あわせて約三一〇万人が死んだあの戦争は、直に戦争を体験していない世代にとっても、強烈な国民的記憶となっている。
ヨーロッパでもアジアでも壮絶な戦いが繰り広げられ、虐殺も横行し、銃後でも様々な葛藤を強いられた。歴史上類を見ない規模で多くの地域、多くの人々が巻き込まれた。
だが人間の歴史のなかで、一言に「戦争」といってもそれは実に多様である。戦いの動機や、戦う人々の様子や、あるいは戦いで用いられる兵器の質、そして戦争それ自体に対する人々の見方は、それぞれの戦争によって全く異なる。
相対的に見るならば、第一次世界大戦や第二次世界大戦などは、むしろ非常に特殊なスタイルの戦争だったとも言えるだろう。その特殊なスタイルとは、一般に「総力戦」と呼ばれる。総力戦は、二〇世紀前半の軍事文化であり、戦争文化だったのである。
「総力戦」にあたる言葉が最初に用いられたのは、第一次大戦末期のフランスにおいてだとされる。だが、一般にその言葉や概念が定着しはじめたのは、ルーデンドルフが『総力戦』を書いた頃、すなわち一九三〇年代半ば以降だと考えられている。
総力戦においては、軍事力だけでなく、軍需生産を支える工業力や食糧確保のための農業生産力も重要となり、それらの生産を支えるために労働力を全面的に動員することになる。老人や女性を含む全国民的な戦争協力が求められるため、それを可能にし正当化するための宣伝と教育にも力が注がれ、思想及びイデオロギーが極めて重要となる。
簡潔に言うならば、総力戦とは、戦闘員と非戦闘員との明確な区別がなくなって交戦諸国のあらゆる人々や資源を総動員して行われる戦争である。
こうしたスタイルの戦争においては、もはや敵軍隊との戦いというよりも、敵国民との戦いという様相を呈するようになっていく。狭義の軍事面だけでなく、財政、商業、生産、国民教育、プロパガンダなどを全面的に指導・調整していくことが求められるようになっていくわけである。
総力戦というスタイルの予兆は、一九世紀中頃からあらわれはじめ、二〇世紀初頭の第一次世界大戦で誰の目にも明らかになった。そして一九三五年のルーデンドルフの著作を皮切りに「総力戦」という概念が一般にも浸透していくようになり、それは第二次世界大戦で頂点に達した、と要約してもよいだろう。
変化していく「戦争」スタイル
二一世紀現在は、中国をはじめとして東アジアにも不安定な要素があるものの、一九四〇年代のような総力戦スタイルで大国間の戦いがおこなわれる可能性は低いとされている。ただしその代わりに、テロやゲリラなど新たな形態への対応が迫られている、というのが今後の状況だとされている。
戦争は時代とともにそのスタイルを変えていく。では一般に、戦争のスタイルや軍事の形を大きく変えていく一番の要因は、いったい何なのだろうか。
軍事における発展や革命といえば、まず私たちの頭に浮かぶのは、科学技術の進歩によるものであろう。火薬、大砲、機関銃、爆撃機、核兵器、ミサイルなど、新しい兵器の登場は、その時代の戦闘と、その後の戦争の様相を大きく変えたことは確かである。
もちろんそこには、狭義の軍事技術だけでなく、内燃機関、電信、鉄道網、精度の高い地図、航空機など、軍事の外側で発明、発展したものも含まれる。こうした科学技術を、軍事における革命の鍵とする議論はよくみられるものである。
また、そうした科学技術の重要性を認めつつも、もっと本質的なのはそれらの「運用」の問題だとする立場から、戦略や戦術、あるいは軍の組織形態などを重視して分析しようとする研究者も多い。
現在の情報通信技術が軍事のあり方を大きく変えていることは、確かに間違いないだろう。それはさしあたりRMAと呼ぶには値するかもしれないが、しかし軍事革命と呼ぶに値するものになるかどうかについては、まだ断言できない。
戦争や軍事は社会全体の動きと連関しているものであるから、軍事上の革命を広く考える際に重要なのは、特定の科学技術や戦略思想にばかり目を向けるのではなく、社会のありようそのものとの関連をよく見ていくことが必要になるのである。
戦争や軍事という営みについて議論される際、しばしば国際政治や軍事技術などに話が集中する傾向にある。だがそれらと同じくらいに重要なのは、人間の行動、振る舞い、あるいは心、情緒、魂など、人間存在そのものに対する洞察なのである。戦争に対する人々の意識こそが、戦争と軍事のあり方を大きく変える。
世俗化していく戦争と軍事
現在、暴力としての戦争に対するタブー意識がこれまでよりも強まってきた結果、今後は狭義の軍事以外の活動がさらに重要視されるようになっていくように思われる。
日本の『防衛白書』でもかなり以前から解説されているように、中国は21世紀の初頭から、「三戦」というものを重視している。三戦とは「輿論戦」、「心理戦」、「法律戦」という三つの非物理的手段をいう。防衛白書ではそれぞれ次のように解説されている。
まず「輿論戦」とは、中国の軍事行動に対する大衆および国際社会の支持を築くとともに、敵が中国の利益に反するとみられる政策を追求することのないよう、国内および国際世論に影響を及ぼすことを目的とするものである。
そして「心理戦」とは、敵の軍人およびそれを支援する文民に対する抑止、衝撃、士気低下を目的とする心理作戦を通じて、敵が戦闘作戦を遂行する能力を低下させようとするものを指す。
「法律戦」とは、国際法および国内法を利用して、国際的な支持を獲得するとともに、中国の軍事行動に対する予想される反発に対処するものである。
このような、以上3つの非物理的手段を軍事と密接に連関させていくことを、現代の中国は極めて重要視しているのである。
『孫子』の有名な一節に、「凡そ用兵の法は、国を全うするを上と為し、国を破るはこれに次ぐ。軍を全うするを上と為し、軍を破るはこれに次ぐ」というのがある。また、「戦わずして人の兵を屈するは善の善なる者なり」という一節も有名である。
戦争は、決して狭義の軍事兵器や軍事戦略だけの問題ではない。要は自分の意思をとおすことが目的なのであるから、戦わないでその目的を達することができれば、それにこしたことはないのである。
もちろん、こうした非物理的手段を軍事と連関させるという考えは、現代中国に限ったものではない。外交、国際交流、いわゆるインテリジェンスの世界など、非軍事分野での活動は昔から大変重要視されてきたし、それが決定的な意味や力をもってきたことは言うまでもない。
しかし今後はそうした活動の対象が、権力者や要職に就いている者に対してだけでなく、より大規模に、そして普通のこととして、一般の老若男女の日常生活にも広がっていくと思われる。軍事に対する人々の見方が敏感になってきたがゆえに、かえって軍事はその裾野を広くして、ゆるやかに日常に浸透していくであろう。
かつて、毛沢東が次のように述べていたのも興味深い。
「中国人民の解放をめざす闘争には、各種の戦線がありますが、なかんずく、文と武の二つの戦線がある、といってよいでしょう。つまり、文化戦線と軍事戦線です。われわれが敵にうち勝つためには、なにはさておき、銃を手にした軍隊にたよらなければなりません。しかし、この軍隊だけでは不十分で、ほかに、文化の軍隊が必要です」(毛沢東著、藤田敬一、吉田富夫訳『遊撃戦論』中公文庫、二〇〇一年、八七頁)
もちろん毛沢東がここで言う「文化の軍隊」の具体的な意味については、慎重に理解されねばならない。詳しい点については省略するが、重要なのは、このように狭義の軍事以外の営みを「戦い」と認識する傾向は、今後ますます強まるであろうということである。
喬良と王湘穂による『超限戦』によれば、「勇ましい武人がわが城を守る」という時代はすでに過去のものだという。そして、今日の世界では、「度の強い近視眼鏡をかけた色白の書生の方が、頭が単純で筋肉の盛り上がっている大男よりもっと現代の軍人にふさわしい」(喬良、王湘穂著、坂井臣之助監修、劉琦訳『超限戦』共同通信社、二〇〇一年、五九頁)と述べている。こうした指摘は、決して大げさなものではないであろう。
古代から現代にかけて、戦闘空間は、陸上、海上、海中、空中、宇宙へと広がってきた。物理的な空間は拡大の一途をたどったが、それらの場所で戦いの主体となるのは、基本的には軍隊であった。
総力戦の時代になると、工場やインフラ、都市部なども標的になった。そこで総力戦の特徴として、戦争の「主体」、すなわち戦闘員と非戦闘員との区別が曖昧になるという点が指摘されてきたわけである。だがこれまでそうした特徴は、あくまでも「戦時」という限られた時間的枠組みの中での話であった。
それに対して、おそらく今後は、戦争の「時間的枠組み」がさらに曖昧になっていくであろう。20世紀的な戦争がもっていた「曖昧さ」は戦闘員と非戦闘員の区別であったが、今後の戦争では、戦時と平時の区別における「曖昧さ」が以前よりも増していくように思われる。それはつまり、薄まった形の戦争が、四六時中日常生活のなかに浸透していくような傾向である。
もちろんそうした傾向は、20世紀においてもある程度すでに見られていた。だがこれからの戦時と平時の区別の曖昧さは、「戦争と平和」の区別そのものについての根本的な問い直しにもつながっていくような、より根本的なものであるだろう。
これは端的に、戦争の世俗化と言ってもよいかもしれない。常に平和であると同時に、常に戦争であり、それはいわば、冷たい総力戦である。
世俗化した戦争においては、戦時と平時の区別が不明確になり、大きな衝突が起きにくいという意味では常に平和であるように見える。ただしその代わりに、小規模な衝突やテロの不安は常に残り、金融、インフラ、あるいはサイバー空間など、一般市民の社会生活が、常にぼんやりとしたゆるい戦場のようになっていく。
経済活動はもちろん、災害派遣も、スポーツも、芸能文化も、シビアな「戦い」の文脈に組み込まれる。これが本当に望ましい人間社会のありようなのかは、まだわからない。だがいずれにしても、戦争のスタイルは、多かれ少なかれ、その時代の人々が自ら選んできたものである。
コントロールしきれない要素も常にあるものだが、そのなかでもどうにかこれまでの戦争を踏まえて、少しでもましな戦争スタイルを模索してきたのが人間の歴史だったのではないだろうか。
今後の軍事的状況を十分に予測せねばならないということは、平和主義の文脈においても言えることである。
戦争に反対することはもちろん正しい。しかし「戦争反対」と叫ぶそのときに想定されている「戦争」が、第二次世界大戦のようなイメージであるならば、特にいま私たちがわざわざ反対などしなくても、そのようなスタイルの戦争は起きないであろう。戦争はその時代ごとに、必ず何かしら新しいスタイルでもって遂行されるものだからである。
すべての戦争は、常にその時代にとって新しい顔で立ち現れてくる。したがって、平和主義とは、現在の戦争スタイルを十分に理解し、また近いうちに戦争が起こるとしたらそれはどういうスタイルの戦争になるかを予測して、それらについて反対することでなければ意味が無いのである。
もし万が一、来年日本が戦争に巻き込まれるとしても、1940年代のような徴兵制や学徒出陣はないであろうし、塹壕戦や銃剣突撃もなければ、特攻隊が編成されることもないだろう。そうした時代とは、軍事行政も、作戦用兵も、軍事兵器も異なる。そして何よりも、戦争に対する国民の考え方が、以前とは全く違うからである。
戦争反対というのは、あくまで現在と未来の戦争に対する反対でなければおかしい。現在の戦争スタイルと次の戦争スタイルをある程度イメージできていて、そこで初めて「戦争反対」は意味をもつ。
だからこそ、一般教養としても、戦争学は大切なはずなのである。
9条を「戦争文化」として捉えよ
今後はさらに、軍事文化の裾野が広がり、戦争という営みはこれまでよりも広く薄まった形で日常に浸透していくであろう。戦時と平時の区別は、かつてよりもさらに不明確になっていく。
そしておそらく今後は、これまでよりも、もっと気軽に、戦争・軍事を学び、あるいは研究しようとする人々が多くあらわれるようになるであろう。
だが、今後戦争や軍事を考えるうえで、狭義の軍事と同じくらいに重要なのは、人間の行動、振る舞い、あるいは心理、情緒、魂など、人間存在そのものに対する洞察なのである。
戦争が悪だということは、今では一部の人々の主張ではなく、ほとんど全員がもっている常識である。だが、そうした常識や感覚の変遷それ自体が、「戦争」と「軍事」の極めて重要な部分なのである。
戦争をもっとも大きく変え、戦争や軍事のあり方が社会のあり方にも影響をおよぼすようになるほど重要なものは、究極的には、戦争という営みに対する人々の考え方、あるいは感性である。
20世紀から21世紀にかけての日本の軍事に関して言うならば、具体的に最も大きな影響力をもったものは、憲法9条である。9条は、単なる言葉・文章に過ぎない。だが現に、良くも悪くも、今の日本の軍事にこれほど大きな影響を与えているものはない。
自衛隊は違憲であるかどうか、海外派遣は是か非か、憲法を改正して自衛隊を自衛軍・日本軍にすべきかどうか、といった様々な議論がなされている。だが9条に肯定的であれ否定的であれ、あるいはその解釈にかなりの幅があるとはいえ、現にそれが、日本の軍事・防衛における極めて大きなファクターとなっていることはまぎれもない事実である。
憲法9条というと、多くの人は、単にそれを「平和主義」の文言として捉えている。しかし、頭から「9条=平和主義」、と捉えてしまう態度そのものが、平和や外交に対する奇妙な「甘え」なのである。
9条は日本の軍事・自衛隊のありように、現に、巨大な影響を与えている。だからそれは、平和の象徴である以前に、現代日本の「戦争文化」、「軍事文化」の一部に他ならないのである。そして日本の軍事に影響を与えている以上、周辺諸国の軍事にも影響を与えていることになる。
9条に対する意見は人によって異なる。だがいずれにしても重要なのは、それをセンチメンタルに「平和主義」の象徴などとして捉えるのではなく、むしろ、良くも悪くも現代日本と近隣諸国の軍事に大きな影響を与えている「戦争文化」の一つであると認識しておくことである。
9条に肯定的な人は、戦争文化としての9条の妥当性を論じてみればよい。9条に否定的な人は、9条の戦争文化としての問題点を論じればよいのである。
戦争は立ち止まらない。軍事は常にその装いを変えていく。戦争は、政治や地理や科学技術のみならず、その時代の人々の平和観にも強く呼応しながら、そのスタイルを常に新たに変えていくのである。
(いしかわ・あきと)



石川明人(北海道大学助教)です。
前回配信したマガジンへのメッセージをいただきました。
EWAT2672さま。コメントありがとうございます。
ご家族のお話を拝読し、私も厳粛な気持ちになりました。
今でも私の実家には、軍人だった祖父の写真があります。それは戦後に撮ったものなので背広姿ですが、とてもやさしい笑顔です。しかし、戦争中の軍服姿の写真には、緊張と厳しさが感じられます。私はもちろん直接戦争を知らない世代の者ですが、せめて人からよくお話を聞き、よく本を読んで、戦争や軍事について考えてみたいと思います。「平和」というのは、究極的には、平時における私たち一人ひとりの、戦争に関するイマジネーションの力にかかっているのかもしれない、とも思うのです。
べーさま。コメントありがとうございます。
べーさまも似た体験をされたことがあるとのこと、慰められる思いです。学校というのはいろいろな意味で特殊な組織ですね。自衛隊と聞いただけで拒否反応を示す教職員ばかりのところもあれば、逆に、学校単位で自衛隊音楽隊のコンサートを聴きに行くところもあるようです。軍人、あるいは自衛官と、一度でも一緒に御飯を食べたり、お酒を飲んだりすれば、彼らが私たちと全く同じ人間であることを実感できるはずです。多くの人がそれを十分感じていれば、かえって過激で無責任な主戦論なども起きにくくなるでしょう。軍人や自衛官との交流は、非常に大切な平和主義的営みだと思っております。
池田さま。コメントありがとうございます。
別の方への返答にも書きましたが、自衛官の方たちと普通に接する機会があれば、彼らに対する偏見がなくなるのみならず、強気だが無責任な主戦論もなくなると思います。自衛官と知り合いになり、その家族を知っていればなおさら、戦争など起きないといいな、と心から思うものだからです。軍人や自衛官一人ひとりの人格・生活・家族などを想像することそれ自体が、とても大切な「平和主義」的佇まいなのだと考えております。
Yさま。メールをありがとうございました。
ご教示をいただき感謝いたします。吉田茂の有名な言葉は防衛大学校卒業式での訓示ではなく、ある一人の方に直接おっしゃった言葉だったとのこと、初めて知りました。資料も教えていただき、大いに納得いたしました。あらためて、御礼を申し上げます。もし今後もお気づきの点がございましたら、ご指導いただけますよう、何卒よろしくお願い申しあげます。
では、【戦争は人間的な営みである】の第5回目をお送りしましょう。
今回のテーマは、「9条もまた戦争文化の一部である」です。戦争や軍事は、政治、経済、科学技術などと密接なものですが、「平和」について人々の抱く考え方それ自体もまた、広い意味では戦争の一部に他ならないと思われます。
忌憚のないご意見、ご感想をいただければ幸甚に存じます。
(参考動画:石川明人「戦争は人間的な営みである」約15分)
http://www.youtube.com/watch?v=gL_de198QsE
************
私たちの「戦争」イメージ
一般に、戦争について考える、あるいは平和について考える、というと、特に私たち日本人の多くは、無意識のうちに、まず第二次世界大戦のような戦争をイメージして話をする傾向が強いであろう。
特攻隊を送り出し、原爆が落とされ、軍民あわせて約三一〇万人が死んだあの戦争は、直に戦争を体験していない世代にとっても、強烈な国民的記憶となっている。
ヨーロッパでもアジアでも壮絶な戦いが繰り広げられ、虐殺も横行し、銃後でも様々な葛藤を強いられた。歴史上類を見ない規模で多くの地域、多くの人々が巻き込まれた。
だが人間の歴史のなかで、一言に「戦争」といってもそれは実に多様である。戦いの動機や、戦う人々の様子や、あるいは戦いで用いられる兵器の質、そして戦争それ自体に対する人々の見方は、それぞれの戦争によって全く異なる。
相対的に見るならば、第一次世界大戦や第二次世界大戦などは、むしろ非常に特殊なスタイルの戦争だったとも言えるだろう。その特殊なスタイルとは、一般に「総力戦」と呼ばれる。総力戦は、二〇世紀前半の軍事文化であり、戦争文化だったのである。
「総力戦」にあたる言葉が最初に用いられたのは、第一次大戦末期のフランスにおいてだとされる。だが、一般にその言葉や概念が定着しはじめたのは、ルーデンドルフが『総力戦』を書いた頃、すなわち一九三〇年代半ば以降だと考えられている。
総力戦においては、軍事力だけでなく、軍需生産を支える工業力や食糧確保のための農業生産力も重要となり、それらの生産を支えるために労働力を全面的に動員することになる。老人や女性を含む全国民的な戦争協力が求められるため、それを可能にし正当化するための宣伝と教育にも力が注がれ、思想及びイデオロギーが極めて重要となる。
簡潔に言うならば、総力戦とは、戦闘員と非戦闘員との明確な区別がなくなって交戦諸国のあらゆる人々や資源を総動員して行われる戦争である。
こうしたスタイルの戦争においては、もはや敵軍隊との戦いというよりも、敵国民との戦いという様相を呈するようになっていく。狭義の軍事面だけでなく、財政、商業、生産、国民教育、プロパガンダなどを全面的に指導・調整していくことが求められるようになっていくわけである。
総力戦というスタイルの予兆は、一九世紀中頃からあらわれはじめ、二〇世紀初頭の第一次世界大戦で誰の目にも明らかになった。そして一九三五年のルーデンドルフの著作を皮切りに「総力戦」という概念が一般にも浸透していくようになり、それは第二次世界大戦で頂点に達した、と要約してもよいだろう。
変化していく「戦争」スタイル
二一世紀現在は、中国をはじめとして東アジアにも不安定な要素があるものの、一九四〇年代のような総力戦スタイルで大国間の戦いがおこなわれる可能性は低いとされている。ただしその代わりに、テロやゲリラなど新たな形態への対応が迫られている、というのが今後の状況だとされている。
戦争は時代とともにそのスタイルを変えていく。では一般に、戦争のスタイルや軍事の形を大きく変えていく一番の要因は、いったい何なのだろうか。
軍事における発展や革命といえば、まず私たちの頭に浮かぶのは、科学技術の進歩によるものであろう。火薬、大砲、機関銃、爆撃機、核兵器、ミサイルなど、新しい兵器の登場は、その時代の戦闘と、その後の戦争の様相を大きく変えたことは確かである。
もちろんそこには、狭義の軍事技術だけでなく、内燃機関、電信、鉄道網、精度の高い地図、航空機など、軍事の外側で発明、発展したものも含まれる。こうした科学技術を、軍事における革命の鍵とする議論はよくみられるものである。
また、そうした科学技術の重要性を認めつつも、もっと本質的なのはそれらの「運用」の問題だとする立場から、戦略や戦術、あるいは軍の組織形態などを重視して分析しようとする研究者も多い。
現在の情報通信技術が軍事のあり方を大きく変えていることは、確かに間違いないだろう。それはさしあたりRMAと呼ぶには値するかもしれないが、しかし軍事革命と呼ぶに値するものになるかどうかについては、まだ断言できない。
戦争や軍事は社会全体の動きと連関しているものであるから、軍事上の革命を広く考える際に重要なのは、特定の科学技術や戦略思想にばかり目を向けるのではなく、社会のありようそのものとの関連をよく見ていくことが必要になるのである。
戦争や軍事という営みについて議論される際、しばしば国際政治や軍事技術などに話が集中する傾向にある。だがそれらと同じくらいに重要なのは、人間の行動、振る舞い、あるいは心、情緒、魂など、人間存在そのものに対する洞察なのである。戦争に対する人々の意識こそが、戦争と軍事のあり方を大きく変える。
世俗化していく戦争と軍事
現在、暴力としての戦争に対するタブー意識がこれまでよりも強まってきた結果、今後は狭義の軍事以外の活動がさらに重要視されるようになっていくように思われる。
日本の『防衛白書』でもかなり以前から解説されているように、中国は21世紀の初頭から、「三戦」というものを重視している。三戦とは「輿論戦」、「心理戦」、「法律戦」という三つの非物理的手段をいう。防衛白書ではそれぞれ次のように解説されている。
まず「輿論戦」とは、中国の軍事行動に対する大衆および国際社会の支持を築くとともに、敵が中国の利益に反するとみられる政策を追求することのないよう、国内および国際世論に影響を及ぼすことを目的とするものである。
そして「心理戦」とは、敵の軍人およびそれを支援する文民に対する抑止、衝撃、士気低下を目的とする心理作戦を通じて、敵が戦闘作戦を遂行する能力を低下させようとするものを指す。
「法律戦」とは、国際法および国内法を利用して、国際的な支持を獲得するとともに、中国の軍事行動に対する予想される反発に対処するものである。
このような、以上3つの非物理的手段を軍事と密接に連関させていくことを、現代の中国は極めて重要視しているのである。
『孫子』の有名な一節に、「凡そ用兵の法は、国を全うするを上と為し、国を破るはこれに次ぐ。軍を全うするを上と為し、軍を破るはこれに次ぐ」というのがある。また、「戦わずして人の兵を屈するは善の善なる者なり」という一節も有名である。
戦争は、決して狭義の軍事兵器や軍事戦略だけの問題ではない。要は自分の意思をとおすことが目的なのであるから、戦わないでその目的を達することができれば、それにこしたことはないのである。
もちろん、こうした非物理的手段を軍事と連関させるという考えは、現代中国に限ったものではない。外交、国際交流、いわゆるインテリジェンスの世界など、非軍事分野での活動は昔から大変重要視されてきたし、それが決定的な意味や力をもってきたことは言うまでもない。
しかし今後はそうした活動の対象が、権力者や要職に就いている者に対してだけでなく、より大規模に、そして普通のこととして、一般の老若男女の日常生活にも広がっていくと思われる。軍事に対する人々の見方が敏感になってきたがゆえに、かえって軍事はその裾野を広くして、ゆるやかに日常に浸透していくであろう。
かつて、毛沢東が次のように述べていたのも興味深い。
「中国人民の解放をめざす闘争には、各種の戦線がありますが、なかんずく、文と武の二つの戦線がある、といってよいでしょう。つまり、文化戦線と軍事戦線です。われわれが敵にうち勝つためには、なにはさておき、銃を手にした軍隊にたよらなければなりません。しかし、この軍隊だけでは不十分で、ほかに、文化の軍隊が必要です」(毛沢東著、藤田敬一、吉田富夫訳『遊撃戦論』中公文庫、二〇〇一年、八七頁)
もちろん毛沢東がここで言う「文化の軍隊」の具体的な意味については、慎重に理解されねばならない。詳しい点については省略するが、重要なのは、このように狭義の軍事以外の営みを「戦い」と認識する傾向は、今後ますます強まるであろうということである。
喬良と王湘穂による『超限戦』によれば、「勇ましい武人がわが城を守る」という時代はすでに過去のものだという。そして、今日の世界では、「度の強い近視眼鏡をかけた色白の書生の方が、頭が単純で筋肉の盛り上がっている大男よりもっと現代の軍人にふさわしい」(喬良、王湘穂著、坂井臣之助監修、劉琦訳『超限戦』共同通信社、二〇〇一年、五九頁)と述べている。こうした指摘は、決して大げさなものではないであろう。
古代から現代にかけて、戦闘空間は、陸上、海上、海中、空中、宇宙へと広がってきた。物理的な空間は拡大の一途をたどったが、それらの場所で戦いの主体となるのは、基本的には軍隊であった。
総力戦の時代になると、工場やインフラ、都市部なども標的になった。そこで総力戦の特徴として、戦争の「主体」、すなわち戦闘員と非戦闘員との区別が曖昧になるという点が指摘されてきたわけである。だがこれまでそうした特徴は、あくまでも「戦時」という限られた時間的枠組みの中での話であった。
それに対して、おそらく今後は、戦争の「時間的枠組み」がさらに曖昧になっていくであろう。20世紀的な戦争がもっていた「曖昧さ」は戦闘員と非戦闘員の区別であったが、今後の戦争では、戦時と平時の区別における「曖昧さ」が以前よりも増していくように思われる。それはつまり、薄まった形の戦争が、四六時中日常生活のなかに浸透していくような傾向である。
もちろんそうした傾向は、20世紀においてもある程度すでに見られていた。だがこれからの戦時と平時の区別の曖昧さは、「戦争と平和」の区別そのものについての根本的な問い直しにもつながっていくような、より根本的なものであるだろう。
これは端的に、戦争の世俗化と言ってもよいかもしれない。常に平和であると同時に、常に戦争であり、それはいわば、冷たい総力戦である。
世俗化した戦争においては、戦時と平時の区別が不明確になり、大きな衝突が起きにくいという意味では常に平和であるように見える。ただしその代わりに、小規模な衝突やテロの不安は常に残り、金融、インフラ、あるいはサイバー空間など、一般市民の社会生活が、常にぼんやりとしたゆるい戦場のようになっていく。
経済活動はもちろん、災害派遣も、スポーツも、芸能文化も、シビアな「戦い」の文脈に組み込まれる。これが本当に望ましい人間社会のありようなのかは、まだわからない。だがいずれにしても、戦争のスタイルは、多かれ少なかれ、その時代の人々が自ら選んできたものである。
コントロールしきれない要素も常にあるものだが、そのなかでもどうにかこれまでの戦争を踏まえて、少しでもましな戦争スタイルを模索してきたのが人間の歴史だったのではないだろうか。
今後の軍事的状況を十分に予測せねばならないということは、平和主義の文脈においても言えることである。
戦争に反対することはもちろん正しい。しかし「戦争反対」と叫ぶそのときに想定されている「戦争」が、第二次世界大戦のようなイメージであるならば、特にいま私たちがわざわざ反対などしなくても、そのようなスタイルの戦争は起きないであろう。戦争はその時代ごとに、必ず何かしら新しいスタイルでもって遂行されるものだからである。
すべての戦争は、常にその時代にとって新しい顔で立ち現れてくる。したがって、平和主義とは、現在の戦争スタイルを十分に理解し、また近いうちに戦争が起こるとしたらそれはどういうスタイルの戦争になるかを予測して、それらについて反対することでなければ意味が無いのである。
もし万が一、来年日本が戦争に巻き込まれるとしても、1940年代のような徴兵制や学徒出陣はないであろうし、塹壕戦や銃剣突撃もなければ、特攻隊が編成されることもないだろう。そうした時代とは、軍事行政も、作戦用兵も、軍事兵器も異なる。そして何よりも、戦争に対する国民の考え方が、以前とは全く違うからである。
戦争反対というのは、あくまで現在と未来の戦争に対する反対でなければおかしい。現在の戦争スタイルと次の戦争スタイルをある程度イメージできていて、そこで初めて「戦争反対」は意味をもつ。
だからこそ、一般教養としても、戦争学は大切なはずなのである。
9条を「戦争文化」として捉えよ
今後はさらに、軍事文化の裾野が広がり、戦争という営みはこれまでよりも広く薄まった形で日常に浸透していくであろう。戦時と平時の区別は、かつてよりもさらに不明確になっていく。
そしておそらく今後は、これまでよりも、もっと気軽に、戦争・軍事を学び、あるいは研究しようとする人々が多くあらわれるようになるであろう。
だが、今後戦争や軍事を考えるうえで、狭義の軍事と同じくらいに重要なのは、人間の行動、振る舞い、あるいは心理、情緒、魂など、人間存在そのものに対する洞察なのである。
戦争が悪だということは、今では一部の人々の主張ではなく、ほとんど全員がもっている常識である。だが、そうした常識や感覚の変遷それ自体が、「戦争」と「軍事」の極めて重要な部分なのである。
戦争をもっとも大きく変え、戦争や軍事のあり方が社会のあり方にも影響をおよぼすようになるほど重要なものは、究極的には、戦争という営みに対する人々の考え方、あるいは感性である。
20世紀から21世紀にかけての日本の軍事に関して言うならば、具体的に最も大きな影響力をもったものは、憲法9条である。9条は、単なる言葉・文章に過ぎない。だが現に、良くも悪くも、今の日本の軍事にこれほど大きな影響を与えているものはない。
自衛隊は違憲であるかどうか、海外派遣は是か非か、憲法を改正して自衛隊を自衛軍・日本軍にすべきかどうか、といった様々な議論がなされている。だが9条に肯定的であれ否定的であれ、あるいはその解釈にかなりの幅があるとはいえ、現にそれが、日本の軍事・防衛における極めて大きなファクターとなっていることはまぎれもない事実である。
憲法9条というと、多くの人は、単にそれを「平和主義」の文言として捉えている。しかし、頭から「9条=平和主義」、と捉えてしまう態度そのものが、平和や外交に対する奇妙な「甘え」なのである。
9条は日本の軍事・自衛隊のありように、現に、巨大な影響を与えている。だからそれは、平和の象徴である以前に、現代日本の「戦争文化」、「軍事文化」の一部に他ならないのである。そして日本の軍事に影響を与えている以上、周辺諸国の軍事にも影響を与えていることになる。
9条に対する意見は人によって異なる。だがいずれにしても重要なのは、それをセンチメンタルに「平和主義」の象徴などとして捉えるのではなく、むしろ、良くも悪くも現代日本と近隣諸国の軍事に大きな影響を与えている「戦争文化」の一つであると認識しておくことである。
9条に肯定的な人は、戦争文化としての9条の妥当性を論じてみればよい。9条に否定的な人は、9条の戦争文化としての問題点を論じればよいのである。
戦争は立ち止まらない。軍事は常にその装いを変えていく。戦争は、政治や地理や科学技術のみならず、その時代の人々の平和観にも強く呼応しながら、そのスタイルを常に新たに変えていくのである。
(いしかわ・あきと)