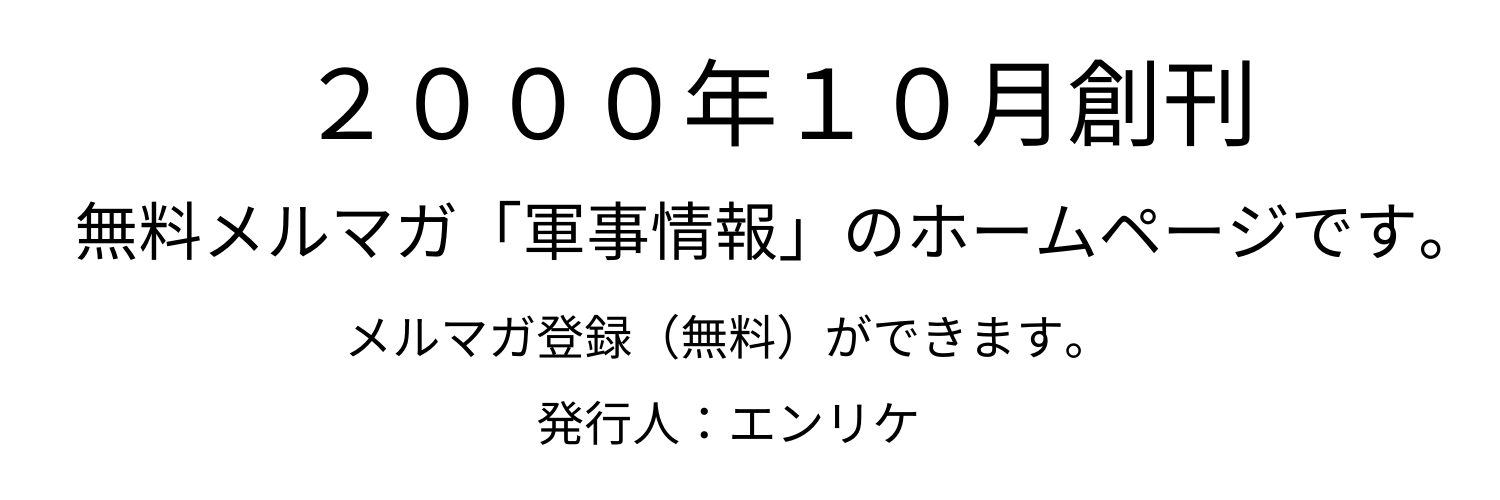人的戦力の充実と特攻戦法の開発–本土決戦準備の真実(20)
丸レ
ごあいさつに代えて ~戦場から届いた言葉~
・・・諸君はたった二ヵ月であったが、帝国軍人として、一生懸命に訓練に励んだ。まことに立派であった。これからは一国民として自らの業務に戻り、国家の復興に尽してほしい。短い間であったが、ともに同じ屋根の下に、同じ釜の飯を食い、起居をともにできたことは、私の生涯の特筆すべき一頁に価することであろう。古代防人の子孫である栃木、茨城の諸君、伝統ある不撓不屈の精神をもって今後来るべき難関を乗り越えていくことを、衷心より祈ってやまない。・・・(昭和20年8月15日、教育隊の初年兵たちへの訓辞)
齋藤 譲(陸軍中尉、近衛歩兵第9連隊・教育隊長)
・・・人間は利や欲だけで動くものではなく、使命を遂行するということに対してより強い喜びを感じ、迷い怠けようとする自らの弱さを克服できる。・・・
西元徹也(元統合幕僚会議議長・陸将)
・・・人は城、人は石垣、人は堀、情けは味方、仇は敵なり。・・・
武田信玄(1521年~1573年 戦国時代の武将)
日本兵法研究会の家村です。それでは、本題に入りましょう。
今回は、日本陸軍が全軍に水際撃滅を徹底させる覚悟を固めた背景にあった大東亜戦争末期における人的戦力の充実と特攻戦法の開発について解説いたします。
三次にわたる兵備下令の達成
水際撃滅は、「水際部における敵の必然的弱点」を徹底して突くという最も理想的な戦い方であるとともに、「国土を寸土たりとも敵にわたさない」という国防精神の観点からも追求すべきものであった。しかし、昭和19年末のレイテ地上決戦を断念した時点では、本土に配置された地上兵備は、動員事務を扱うだけの留守師団12コを含めて20コ師団と9コ独立混成旅団にすぎなかった。
こうした貧弱な兵備から、水際撃滅は実行の可能性に鑑みてこれを断念せざるを得なかった。最終的に水際撃滅を可能にしたものが、「50コ師団急速大動員(根こそぎ動員)」の予想外の進展と、人命と引替に敵戦力を屠(ほふ)らんとする「特攻戦法の開発」であった。
大本営陸軍部は、「超非常手段を必要とする絶体絶命の本土決戦に臨む」という認識の下に陸軍省との交渉を重ね、師団44コ、独立混成旅団16コ、戦車旅団6コを五ヵ月の間に急増する大動員計画を立案し、三次にわたる兵備下令としてこれを実行に移した。昭和19年12月末から昭和20年1月にかけて、以前から計画されていた9コ師団が新編されたが、その後の急速動員は以下のとおりに進められた。
応急動員(1月中旬から3月上旬):5コ独立混成旅団
第一次動員(2月中旬から5月上旬):18コ歩兵師団
第二次動員(4月上旬から5月下旬):8コ歩兵師団、6コ戦車旅団
第三次動員(5月中旬から8月上旬):19コ歩兵師団、15コ独立混成旅団
第一次及び第三次動員における歩兵師団は、いずれも沿岸配備師団であるのに対し、第二次動員における8コ歩兵師団は、全て機動打撃(決戦)兵団であり、敵の制空権下での機動を考慮して高射火器(20mm連装高射機関砲×9門)を装備するとともに、榴弾砲・山砲や迫撃砲を多く配備した。又、この決戦兵団の将兵には若年気鋭の者を充当し、特に師団長には階級序列にかかわらず適任者を選考した。
これらは、戦闘員150万人、兵站部隊以下を加えると200万人という陸軍始まって以来の大規模動員であり、更に海軍の動員を加えると総計250万人に達する計算であった。当初はほとんど不可能と思われたこの大動員は予想外に進展し、7月中旬を予定していた第三次兵備下令は2ヵ月も繰り上げられた。
これに加え、3月中旬から下旬にかけて満州から1コ戦車師団と3コ歩兵師団が決戦兵団として本土に転用された。いずれも米軍が恐れていた精鋭関東軍の現役師団であり、その内訳は、戦車第1師団が千葉へ、第11師団が四国へ、第25師団及び第57師団が南九州へと移駐し、それぞれの方面軍に編入された。
こうして8月を迎える頃には、本州、四国、九州の予想戦場に配置された地上兵力は、師団53コ、独立混成旅団22コ、戦車師団2コ、戦車旅団7コ、高射砲師団4コ、警備旅団3コとなり、兵力合計も概ね予定した数に達していた。
国内戦に備えた軍令・軍政機構の構築
本土における作戦部隊の急増に対応するため、昭和20年1月下旬から2月上旬、6コ方面軍司令部が新編され、同時に軍政を担当する軍管区が方面軍と対応するように設定された。北から第5方面軍(北部軍管区)、第11方面軍(東北軍管区)、第12方面軍(東部軍管区)、第13方面軍(東海軍管区)、第15方面軍(中部軍管区)、第16方面軍(西部軍管区)である。こうして、外地における作戦と同様に国内でも作戦軍の一部が軍政を担う体制が整った。
さらに4月15日には、各方面軍を束ねる総軍が設けられた。東日本を統括する第1総軍と西日本を統括する第2総軍であり、これらは滋賀・岐阜の県境から鈴鹿山地にかけて相互の境界線とした。これに加え、全国規模で航空作戦を統括する航空総軍も発足した。これにより、大本営が直接各方面軍司令官を指揮することなく、総軍司令官に対して命令することとなった。
兵力の短期・大増強を可能にした国民皆兵制度の改訂
このような短期間の兵力大増強を可能にしたものは、当時の国民皆兵制度である。当時の日本では、満17歳から満40歳までの男子総てに兵役義務があったが、大東亜戦争間の所要兵力の増大に伴い、この兵役制度は以下のように逐次改訂されていった。
まず、開戦の約一ヶ月前である昭和16年11月15日には、充員召集対象がそれまでの予備役・補充兵から、服役年限を終えた第一国民兵や徴兵検査で丙種合格(不合格ギリギリで合格)の第二国民兵にまで拡大された。
昭和18年10月2日、それまで在学徴集延期特例により、徴兵が猶予されていた文系学生に対しても、この徴兵猶予が停止され、同年10月13日、兵役年齢の上限が40歳から45歳に引き上げられた。さらに同年12月24日には、徴兵適齢が20歳から19歳に引き下げられた。
昭和19年10月18日、徴兵検査前の17歳以上の者は全て兵籍に編入され、召集の対象となった。また、同年11月14日には、17歳以下でも志願により兵籍への編入が可能となった。
昭和20年2月9日、徴兵検査未受検の第二国民兵に対して、召集時の徴兵検査が延期された。こうして、日本人の45歳以下の男子はほとんど全て兵員となり得る体制が出来上がった。
対戦車特攻戦法の開発
このように、所要の兵力を得ることができたにもかかわらず、陸軍150万の戦闘員に対して小銃は全国から掻き集めても70万挺しかなく、更に機関銃は所要数の23%、歩兵砲は28%しかなかった。国家のじり貧の生産力のほとんどは、特攻舟艇や、特攻用航空機の生産に向けられており、小銃や機関銃といった小火器の生産にまわすだけの余力はなかった。つまり、新たな兵力の半分は小銃・銃剣すら持たない「丸腰」で戦わねばならないのが実情であった。
また、第三次新設師団の兵隊のほとんどは、新兵としての教育すらなされていない補充兵であり、各連隊の将校は数名にすぎなかったが、徴兵地域と輸送力との関係上これらの師団でさえも多くは重要正面における沿岸配備任務を与えざるを得なかった。
指揮官も装備も所要の半分に達しないこれらの兵団を有効な戦力として活用し、上陸と同時に大量の戦車を投入して突進して来る敵を撃破する手段は唯一つしかなかった。それは、戦車を相手とした「一人一輛必砕」の肉薄攻撃であった。
大本営陸軍部は、7月16日『決号作戦における対戦車戦闘要綱』を全軍に発令布告し、歩兵・工兵は勿論、通信兵、兵站部員等でも対戦車爆弾を所持して、肉薄攻撃を敢行することを要求した。攻撃方法は数種類あったが、500gの黄色火薬を装填した爆弾を10m以内で投擲するのを一般方式とし、その爆弾に柄をつけた刺突爆弾や、火炎瓶、または黄色火薬10Kgを背負って戦車のキャタピラの下に突入する自爆方式等が採用された。たとえ小銃さえ撃ったことのない兵の集まりでも、こうした方式を大規模かつ徹底的に断行することができれば、敵の損害は莫大であったろうと予想された。
海軍の特攻作戦準備
この時期、すでに艦隊のほとんどを失っていた海軍は、敵の上陸船団が本土に来航したならば、敵の上陸に先立ちその半数を海上で撃沈できるように、航空特攻及び水上水中特攻を準備していた。
航空特攻については、昭和20年7月15日までに特攻機3000機を整備(実働2500機)し、その攻撃目標を敵輸送船団としたが、そのうち敵機動部隊の攻撃にも性能に優れた実用機300機(実働200機)を向けるとともに、これを直接掩護するための戦闘機400機を待機させていた。
水上水中特攻については、昭和20年7月末の時点で、北海道を除く全国の太平洋岸に小型潜水艦「蛟龍」・潜航艇「海龍」308隻、人間魚雷「回天」118隻、特攻艇「震洋」2375隻を展開していた。そのうち関東正面の作戦に備え、「蛟龍」「海龍」156隻、「回天」24隻、「震洋」675隻を下田、油壺、勝浦などに構築した洞窟式格納庫に配備していた。又、人員が水中に待機して敵上陸用舟艇の底部を刺突式の機雷で破壊する「伏龍」も多数準備されていた。
これらに加え、海軍は陸戦に備えて6コの連合特別陸戦隊を新編したが、その総兵員数は陸軍の新設歩兵師団10個分を上回る規模以上であったものと推察される。
特攻兵器ではなかった「丸レ」
本稿にも幾度か登場した陸軍の海上挺身攻撃艇「丸レ」について、海軍の特攻艇「震洋」と外形が類似していることから、これを「特攻兵器」と誤解されることが多い。しかし、同じ全長6m前後のモーターボートであっても、「震洋」がその頭部に爆薬を取り付け、敵艦に体当たりする「必死必中」の特攻兵器であるのに対して、「丸レ」は操縦席の後方に2個の120Kg爆雷を装着し、敵艦近くで投下して爆発させる仕組みであり、生還できる可能性のある兵器であった。しかし、実際には敵艦からの機銃の猛射をすり抜けて接近し、敵艦の直前に爆雷を投下するという極めて危険な任務を遂行する中で、
負傷して艇とともに体当たりしたケースも多々あった。
本土決戦に備え、「震洋」が本土全域に配置されていたのに対し、フィリピン戦線で奮戦した「丸レ」は、本土決戦用に800隻が九州に重点配備されていた。
(以下次号)
(いえむら・かずゆき)
※この連載を、第一回からふたたびメルマガでお楽しみいただけます。
【本土決戦準備の真実 -日本陸軍はなぜ水際撃滅に帰結したのか-】
登録はこちらから(無料)
ごあいさつに代えて ~戦場から届いた言葉~
・・・諸君はたった二ヵ月であったが、帝国軍人として、一生懸命に訓練に励んだ。まことに立派であった。これからは一国民として自らの業務に戻り、国家の復興に尽してほしい。短い間であったが、ともに同じ屋根の下に、同じ釜の飯を食い、起居をともにできたことは、私の生涯の特筆すべき一頁に価することであろう。古代防人の子孫である栃木、茨城の諸君、伝統ある不撓不屈の精神をもって今後来るべき難関を乗り越えていくことを、衷心より祈ってやまない。・・・(昭和20年8月15日、教育隊の初年兵たちへの訓辞)
齋藤 譲(陸軍中尉、近衛歩兵第9連隊・教育隊長)
・・・人間は利や欲だけで動くものではなく、使命を遂行するということに対してより強い喜びを感じ、迷い怠けようとする自らの弱さを克服できる。・・・
西元徹也(元統合幕僚会議議長・陸将)
・・・人は城、人は石垣、人は堀、情けは味方、仇は敵なり。・・・
武田信玄(1521年~1573年 戦国時代の武将)
日本兵法研究会の家村です。それでは、本題に入りましょう。
今回は、日本陸軍が全軍に水際撃滅を徹底させる覚悟を固めた背景にあった大東亜戦争末期における人的戦力の充実と特攻戦法の開発について解説いたします。
三次にわたる兵備下令の達成
水際撃滅は、「水際部における敵の必然的弱点」を徹底して突くという最も理想的な戦い方であるとともに、「国土を寸土たりとも敵にわたさない」という国防精神の観点からも追求すべきものであった。しかし、昭和19年末のレイテ地上決戦を断念した時点では、本土に配置された地上兵備は、動員事務を扱うだけの留守師団12コを含めて20コ師団と9コ独立混成旅団にすぎなかった。
こうした貧弱な兵備から、水際撃滅は実行の可能性に鑑みてこれを断念せざるを得なかった。最終的に水際撃滅を可能にしたものが、「50コ師団急速大動員(根こそぎ動員)」の予想外の進展と、人命と引替に敵戦力を屠(ほふ)らんとする「特攻戦法の開発」であった。
大本営陸軍部は、「超非常手段を必要とする絶体絶命の本土決戦に臨む」という認識の下に陸軍省との交渉を重ね、師団44コ、独立混成旅団16コ、戦車旅団6コを五ヵ月の間に急増する大動員計画を立案し、三次にわたる兵備下令としてこれを実行に移した。昭和19年12月末から昭和20年1月にかけて、以前から計画されていた9コ師団が新編されたが、その後の急速動員は以下のとおりに進められた。
応急動員(1月中旬から3月上旬):5コ独立混成旅団
第一次動員(2月中旬から5月上旬):18コ歩兵師団
第二次動員(4月上旬から5月下旬):8コ歩兵師団、6コ戦車旅団
第三次動員(5月中旬から8月上旬):19コ歩兵師団、15コ独立混成旅団
第一次及び第三次動員における歩兵師団は、いずれも沿岸配備師団であるのに対し、第二次動員における8コ歩兵師団は、全て機動打撃(決戦)兵団であり、敵の制空権下での機動を考慮して高射火器(20mm連装高射機関砲×9門)を装備するとともに、榴弾砲・山砲や迫撃砲を多く配備した。又、この決戦兵団の将兵には若年気鋭の者を充当し、特に師団長には階級序列にかかわらず適任者を選考した。
これらは、戦闘員150万人、兵站部隊以下を加えると200万人という陸軍始まって以来の大規模動員であり、更に海軍の動員を加えると総計250万人に達する計算であった。当初はほとんど不可能と思われたこの大動員は予想外に進展し、7月中旬を予定していた第三次兵備下令は2ヵ月も繰り上げられた。
これに加え、3月中旬から下旬にかけて満州から1コ戦車師団と3コ歩兵師団が決戦兵団として本土に転用された。いずれも米軍が恐れていた精鋭関東軍の現役師団であり、その内訳は、戦車第1師団が千葉へ、第11師団が四国へ、第25師団及び第57師団が南九州へと移駐し、それぞれの方面軍に編入された。
こうして8月を迎える頃には、本州、四国、九州の予想戦場に配置された地上兵力は、師団53コ、独立混成旅団22コ、戦車師団2コ、戦車旅団7コ、高射砲師団4コ、警備旅団3コとなり、兵力合計も概ね予定した数に達していた。
国内戦に備えた軍令・軍政機構の構築
本土における作戦部隊の急増に対応するため、昭和20年1月下旬から2月上旬、6コ方面軍司令部が新編され、同時に軍政を担当する軍管区が方面軍と対応するように設定された。北から第5方面軍(北部軍管区)、第11方面軍(東北軍管区)、第12方面軍(東部軍管区)、第13方面軍(東海軍管区)、第15方面軍(中部軍管区)、第16方面軍(西部軍管区)である。こうして、外地における作戦と同様に国内でも作戦軍の一部が軍政を担う体制が整った。
さらに4月15日には、各方面軍を束ねる総軍が設けられた。東日本を統括する第1総軍と西日本を統括する第2総軍であり、これらは滋賀・岐阜の県境から鈴鹿山地にかけて相互の境界線とした。これに加え、全国規模で航空作戦を統括する航空総軍も発足した。これにより、大本営が直接各方面軍司令官を指揮することなく、総軍司令官に対して命令することとなった。
兵力の短期・大増強を可能にした国民皆兵制度の改訂
このような短期間の兵力大増強を可能にしたものは、当時の国民皆兵制度である。当時の日本では、満17歳から満40歳までの男子総てに兵役義務があったが、大東亜戦争間の所要兵力の増大に伴い、この兵役制度は以下のように逐次改訂されていった。
まず、開戦の約一ヶ月前である昭和16年11月15日には、充員召集対象がそれまでの予備役・補充兵から、服役年限を終えた第一国民兵や徴兵検査で丙種合格(不合格ギリギリで合格)の第二国民兵にまで拡大された。
昭和18年10月2日、それまで在学徴集延期特例により、徴兵が猶予されていた文系学生に対しても、この徴兵猶予が停止され、同年10月13日、兵役年齢の上限が40歳から45歳に引き上げられた。さらに同年12月24日には、徴兵適齢が20歳から19歳に引き下げられた。
昭和19年10月18日、徴兵検査前の17歳以上の者は全て兵籍に編入され、召集の対象となった。また、同年11月14日には、17歳以下でも志願により兵籍への編入が可能となった。
昭和20年2月9日、徴兵検査未受検の第二国民兵に対して、召集時の徴兵検査が延期された。こうして、日本人の45歳以下の男子はほとんど全て兵員となり得る体制が出来上がった。
対戦車特攻戦法の開発
このように、所要の兵力を得ることができたにもかかわらず、陸軍150万の戦闘員に対して小銃は全国から掻き集めても70万挺しかなく、更に機関銃は所要数の23%、歩兵砲は28%しかなかった。国家のじり貧の生産力のほとんどは、特攻舟艇や、特攻用航空機の生産に向けられており、小銃や機関銃といった小火器の生産にまわすだけの余力はなかった。つまり、新たな兵力の半分は小銃・銃剣すら持たない「丸腰」で戦わねばならないのが実情であった。
また、第三次新設師団の兵隊のほとんどは、新兵としての教育すらなされていない補充兵であり、各連隊の将校は数名にすぎなかったが、徴兵地域と輸送力との関係上これらの師団でさえも多くは重要正面における沿岸配備任務を与えざるを得なかった。
指揮官も装備も所要の半分に達しないこれらの兵団を有効な戦力として活用し、上陸と同時に大量の戦車を投入して突進して来る敵を撃破する手段は唯一つしかなかった。それは、戦車を相手とした「一人一輛必砕」の肉薄攻撃であった。
大本営陸軍部は、7月16日『決号作戦における対戦車戦闘要綱』を全軍に発令布告し、歩兵・工兵は勿論、通信兵、兵站部員等でも対戦車爆弾を所持して、肉薄攻撃を敢行することを要求した。攻撃方法は数種類あったが、500gの黄色火薬を装填した爆弾を10m以内で投擲するのを一般方式とし、その爆弾に柄をつけた刺突爆弾や、火炎瓶、または黄色火薬10Kgを背負って戦車のキャタピラの下に突入する自爆方式等が採用された。たとえ小銃さえ撃ったことのない兵の集まりでも、こうした方式を大規模かつ徹底的に断行することができれば、敵の損害は莫大であったろうと予想された。
海軍の特攻作戦準備
この時期、すでに艦隊のほとんどを失っていた海軍は、敵の上陸船団が本土に来航したならば、敵の上陸に先立ちその半数を海上で撃沈できるように、航空特攻及び水上水中特攻を準備していた。
航空特攻については、昭和20年7月15日までに特攻機3000機を整備(実働2500機)し、その攻撃目標を敵輸送船団としたが、そのうち敵機動部隊の攻撃にも性能に優れた実用機300機(実働200機)を向けるとともに、これを直接掩護するための戦闘機400機を待機させていた。
水上水中特攻については、昭和20年7月末の時点で、北海道を除く全国の太平洋岸に小型潜水艦「蛟龍」・潜航艇「海龍」308隻、人間魚雷「回天」118隻、特攻艇「震洋」2375隻を展開していた。そのうち関東正面の作戦に備え、「蛟龍」「海龍」156隻、「回天」24隻、「震洋」675隻を下田、油壺、勝浦などに構築した洞窟式格納庫に配備していた。又、人員が水中に待機して敵上陸用舟艇の底部を刺突式の機雷で破壊する「伏龍」も多数準備されていた。
これらに加え、海軍は陸戦に備えて6コの連合特別陸戦隊を新編したが、その総兵員数は陸軍の新設歩兵師団10個分を上回る規模以上であったものと推察される。
特攻兵器ではなかった「丸レ」
本稿にも幾度か登場した陸軍の海上挺身攻撃艇「丸レ」について、海軍の特攻艇「震洋」と外形が類似していることから、これを「特攻兵器」と誤解されることが多い。しかし、同じ全長6m前後のモーターボートであっても、「震洋」がその頭部に爆薬を取り付け、敵艦に体当たりする「必死必中」の特攻兵器であるのに対して、「丸レ」は操縦席の後方に2個の120Kg爆雷を装着し、敵艦近くで投下して爆発させる仕組みであり、生還できる可能性のある兵器であった。しかし、実際には敵艦からの機銃の猛射をすり抜けて接近し、敵艦の直前に爆雷を投下するという極めて危険な任務を遂行する中で、
負傷して艇とともに体当たりしたケースも多々あった。
本土決戦に備え、「震洋」が本土全域に配置されていたのに対し、フィリピン戦線で奮戦した「丸レ」は、本土決戦用に800隻が九州に重点配備されていた。
(以下次号)
(いえむら・かずゆき)
※この連載を、第一回からふたたびメルマガでお楽しみいただけます。
【本土決戦準備の真実 -日本陸軍はなぜ水際撃滅に帰結したのか-】
登録はこちらから(無料)