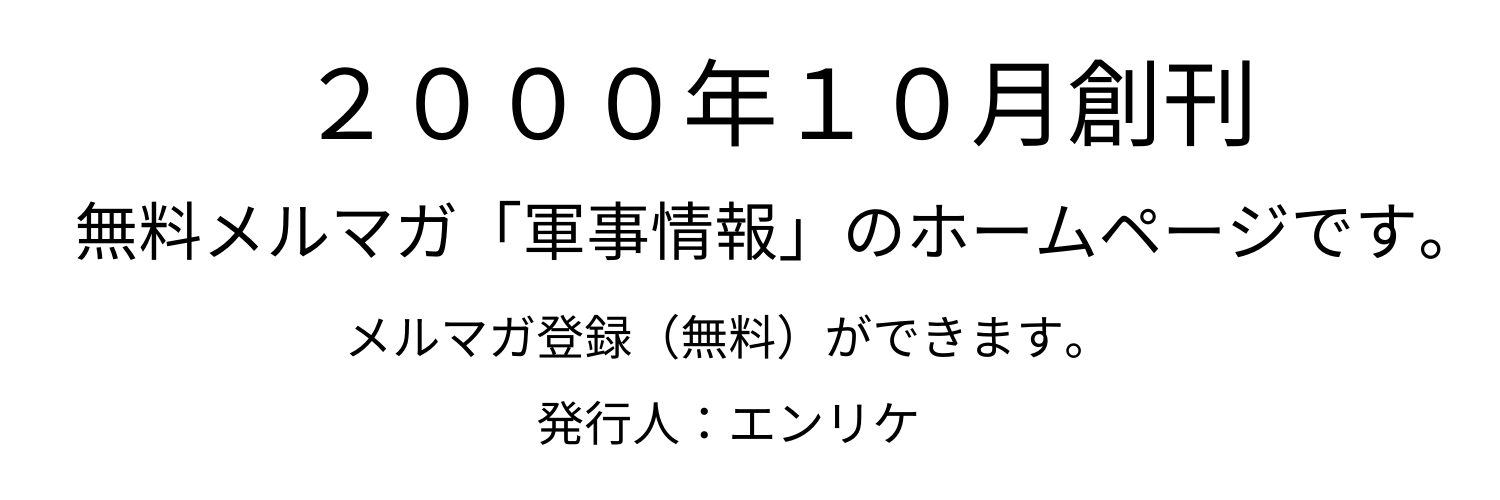トーチ作戦とインテリジェンス(15) ~ウィリアム・ドノヴァンの略歴とその活動(2)~
From:長南政義
こんにちは。長南です。
本連載は、トーチ作戦(*)までのフランス領北アフリカにおける、米国務省と共同実施した連合国の戦略作戦情報の役割についての考察です。
(*)1940年から1942年11月8日に実施された、連合国軍によるモロッコおよびアルジェリアへの上陸作戦のコードネーム。トーチとは「たいまつ」の意味
前回は、ウィリアム・ドノヴァンの略歴について述べました。
「CIAの父」との異名を持つウィリアム・ジョセフ・“ワイルド・ビル”・ドノヴァンは、ニューヨーク州のバッファローでアイルランド系移民の子として生まれました。コロンビア・ロー・スクールを卒業後、ウォール街における有力な弁護士の一人になります。
第一次世界大戦が勃発すると陸軍少佐として欧州大陸に出征し、米軍において最高位の勲章である名誉勲章を受章しました。終戦までに陸軍大佐に昇進し、殊勲十字章と名誉戦傷章も受章。軍人としても有能でした。
ルーズヴェルトがドノヴァンと最初に会ったのは、ルーズヴェルトが海軍次官のポストについていた戦間期のことです。二人の関係は1933年にルーズヴェルトが大統領に就任した後も続きました。
ドノヴァンは、1935年から1936年にかけて、イタリア陸軍とその作戦活動を視察するためエチオピアを訪問しています。さらに、ルーズヴェルト大統領の命を受けて内戦下のスペインを視察していました。
視察旅行を通じてドノヴァンは、諜報活動がいかに重要かを明確に認識するようになります。そして、新たなる大戦においては、敵国の諜報活動が米国内で活発に展開されるような事態にさせてはいけない、と決意するようになったのです。
1940年7月16日、ルーズヴェルト大統領は、英国の防衛体制に関する再調査を行わせるためドノヴァンを英国に派遣します。この当時、ナチス・ドイツは、英国本土に対する上陸作戦(作戦名:あしか作戦)を実行しようとしており、あしか作戦の前哨戦として7月10日から、「バトル・オブ・ブリテン」(*)が英独両軍間で展開されていました。
(*)英国本土の制空権獲得を目的とした航空戦
ドノヴァンは、ルーズヴェルト大統領から、英国がドイツの侵略に耐えうるか否かを調査せよとの命を受け、ドイツ空軍の空襲を耐え抜く英国の耐久力や抗戦意志を確かめるために英国本土へ送り出されたのです。
視察を終え米国に帰還したドノヴァンは、英国がドイツ軍の攻撃に物理的に耐えうることが可能であるだけでなく、英国首相ウィンストン・チャーチルが英国民の抗戦意志の鼓舞に成功しているとの報告をルーズヴェルトに提出するのですが。。。
トーチ作戦とインテリジェンス(15) ~ウィリアム・ドノヴァンの略歴とその活動(2)~
■□正反対だったドノヴァン報告
しかし、英国の継戦意志および能力に関するドノヴァンによるこの情勢分析は、ジョン・F・ケネディの父である当時の駐英米国大使ジョセフ・パトリック・“ジョー”・ケネディの分析と全く正反対のものであった。
ジョー・ケネディは、ナチス・ドイツの電撃戦の前にもろくも敗れ去ったフランスのように、英国が、ナチス・ドイツの強大な軍事力の前に抗戦能力に対する自信と戦意を失い、最終的には降伏するかもしれないと憂慮していたのである。
さらに、ジョー・ケネディは、英国は米国からの支援なくしてはドイツ空軍の猛攻撃を耐えることができないと、ルーズヴェルト大統領に報告していた。
■□マインドセットの罠
ジョー・ケネディはなぜナチス・ドイツの力を過大評価してしまったのであろうか。そもそも、ジョー・ケネディの姿勢は、英国赴任当時からナチス・ドイツ寄りであった。ジョー・ケネディが駐英米国大使となったのは1938年のことであったが、彼は当時の英国首相ネヴィル・チェンバレンによる宥和政策を支持し、アドルフ・ヒトラーの政策に一定程度の理解を示していたのである。ジョー・ケネディは、米国による孤立主義の堅持とナチス・ドイツに対する譲歩とが第二の世界大戦を回避可能な唯一の方法と考えていたのである。
ナチスによるホロコーストの報道がなされるようになっても、ジョー・ケネディは、ヒトラーとの直接会談を通じて事態を好転できることが可能であると考えていた。甘い見通しというべきであろう。
第二次世界大戦が始まると、ジョー・ケネディは、英国に対する武器供与に反対した。さらに、バトル・オブ・ブリテンが始まるや、首都ロンドンから疎開することのなかった英国王室及び英国政府の落ち着いた態度とは正反対に、ジョー・ケネディはロンドンを離れ地方に疎開し、英国民から嘲笑されている。
以上述べたような、ジョー・ケネディの態度、彼から提出された英国の将来を不安視する内容の報告書、及びその無思慮で軽率な言動のため、ルーズヴェルト大統領は、その後、ジョー・ケネディを本国に召還することとなる。
ジョー・ケネディの情勢分析はなぜナチス・ドイツの軍事力を過大評価するものであったのだろうか。インテリジェンスの分野では、情報分析をゆがめてしまう要因の一つとして、マインドセットが挙げられることがある。
マインドセットとは、分析官が無意識的にある一定の考え方や思い込みに陥ることを意味する専門用語である。ジョー・ケネディは、駐英米国大使でありながら、赴任当初の1938年からヒトラーへの譲歩を主張するなど、ナチス・ドイツ寄りの発言を続けてきた。
ジョー・ケネディの心の奥底に存在したナチス・ドイツに対する過大な警戒心や恐れが、ナチス・ドイツに対する軍事力の過大評価を無意識のうちに招いてしまった原因の一つであったといえるであろう。換言するならば、彼はマインドセットの罠にはまっており、正確な分析ができなかったのである。
ジョー・ケネディは、自身が果たせなかった大統領に就任するという野望を自身の息子に託したことで有名である。駐英米国大使という官職だけではなく、大統領就任というジョー・ケネディの夢を打ち砕いたのは、自身のマインドセットだった。
1940年11月10日のボストン・グローブ紙に、以下のようなジョー・ケネディの談話が掲載された。
「英国に武器を供与する最大の目的はとにかく時間を稼ぐこと、準備する時間を稼ぐことだ。イギリスは別に民主主義のためにナチスと戦っているのではない、ただ自己保存の戦いをしているのだ」
この記事は米国民からの批判を招くに十分すぎるほどのインパクトがあった。国内外からの批判の声を前に、ルーズヴェルト大統領は、ジョー・ケネディをこれ以上大使の職に留任させることは不可能と判断し、1940年11月にジョー・ケネディを辞任に追い込んだのである。これにより、ジョー・ケネディの政治生命も事実上絶たれたのであった。
■□ただ一人の中央情報局(CIA)
マインドセットの陥穽に落ちたジョー・ケネディの情勢分析とは対照的に、ドノヴァンの情勢分析はバイアスがかかっておらず偏向が少ないものであった。この点が、ルーズヴェルト大統領の目に留まった。
ルーズヴェルトは、情勢を正確に分析し、そのままでは使うことの出来ないインフォメーション(データや生情報の類)をインテリジェンス(何らかの判断や評価が加えられた情報)へと高めることのできる才能をドノヴァンのなかに見出した。
本連載で既述したように、この当時の米国では、FBI、米国陸軍情報局および米国海軍情報局という三つの主要なインテリジェンス機関が存在したため、各機関のインテリジェンス活動が重複するという弊害が生じていた。そのため、ルーズヴェルトは、インテリジェンス機関同士の活動を調整しようとしていたが、ドノヴァンは、英国視察を通じて、次第に大統領の個人的な中央情報機関という役割を果たすようになっていった。
後のCIA長官ウィリアム・ケーシーが指摘しているように、ドノヴァンの英国視察旅行は、ドノヴァンを「ルーズヴェルト大統領にとってただ一人の中央情報局」にする結果をもたらしたのである(トーマス・F・トロイ『ワイルド・ビルとイントレピッド ~ドノヴァン、スティーヴンスンおよびCIAの起源~』原題:Wild Bill and Intrepid Donovan, Stephenson, and the Origin of CIA.)。
■□インテリジェンス・サイクルとドノヴァンの情報収集活動
ドノヴァンは、大統領から要求された時にルーズヴェルト大統領にとっての唯一の中央情報機関としての役割を果たすだけでなく、将来的に米軍の作戦が展開される可能性の高い地域の出来事に関する戦略レヴェルの情報収集を個人的に行ってもいた。
ルーズヴェルト大統領は、詳細かつ正確なインテリジェンスを欲していた。情報に飢えていたのである。そのため、ルーズヴェルト大統領は、ドノヴァンが各地域に情報収集旅行を行うに際して、自身が望むインテリジェンスに関する明確な指針をドノヴァンに与えていた。
現代のインテリジェンスには、
(1)リクワイアメント(情報ニーズ)→(2)情報収集→(3)情報分析・評価→(4)インテリジェンスの配布→(5)フィードバック
というインテリジェンス・サイクルが存在する。インテリジェンス・サイクルがうまく機能するためには、インテリジェンスを必要とする政策立案・決定者の側が、明確な情報ニーズを情報機関の側に出す必要がある。すべては情報カスタマーである政策決定者の情報ニーズから始まるのである。
ルーズヴェルト大統領がドノヴァンに与えていた明確な情報収集に関する指針は、現代のリクワイアメント(情報ニーズ)に相当するものであった。ドノヴァンの集めた情報の価値が戦略的に高かった理由は、ルーズヴェルトが明確なリクワイアメント(情報ニーズ)をドノヴァンに与えた点にあったといえるであろう。
(以下次号)
(ちょうなん・まさよし)