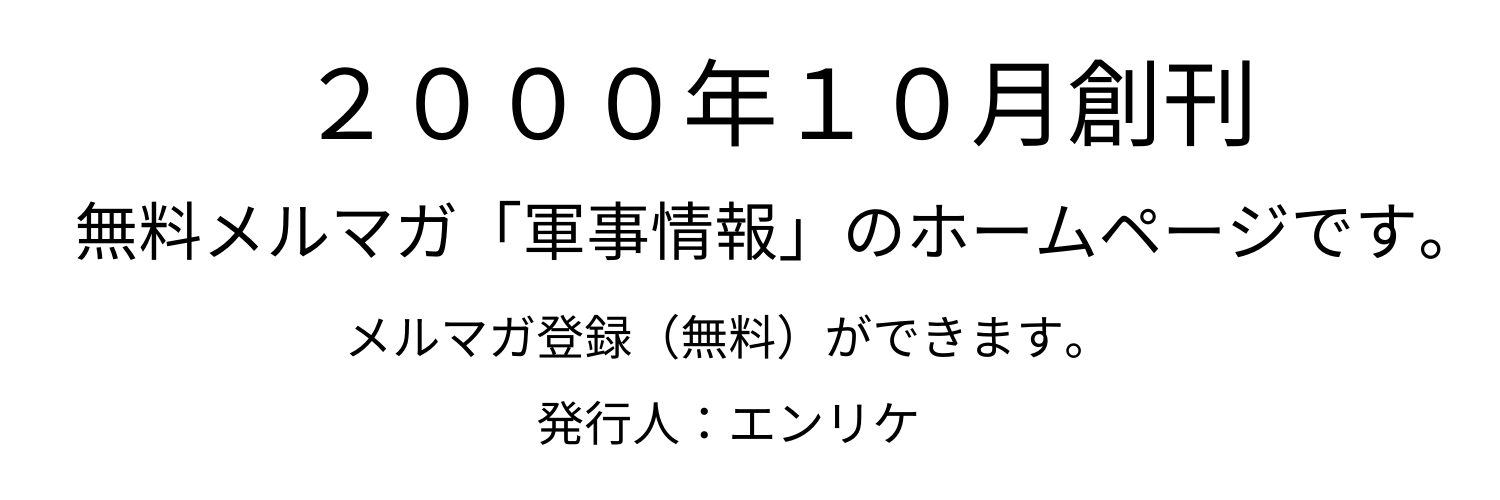戦傷者 Part3–フランス外人部隊・日本人衛生兵のアフガニスタン戦争 Vol.34
はじめに
読者様より質問をいただきました。ありがとうございます。
質問内容は、外人部隊における軍医の採用についてです。
外人部隊の軍医もフランス正規軍の軍医も、フランス軍の医大を出て、軍の病院で研修医をやったあと各部隊に配属されています。ですから、皆フランス人です。
医師免許を持った外人が外人部隊に入っても、軍医になれるわけではありません。しかし、衛生隊員には優先してならせてもらえると思います。そんな後輩が1人いました。
ちなみに、衛生兵教育の一環で、私が軍病院で実習していたとき、2人の研修医がいましたが、25歳で「中尉」の階級でした。私は当時27歳で一等兵でした・・・。
戦傷者Part3
負傷者の救命活動にあたるプルキエ少佐とミッサニ伍長に私が合流することで、2つ目の気管切開キットが少佐に手渡された。
少佐は点滴用チューブを切って作った気道用の管を負傷者の喉から取りはずし、気管切開キットに入っている気管カニューレというチューブを差し込んだ。
そして、2つ目のチューブは絶対に脱落させまいと、縫合用の針と糸でチューブのストッパーのヒレの部分を、首の皮膚に縫い付けはじめた。
その作業をやりながら、少佐は私とミッサニに指示を出す。私は合流したばかりで、状況がはっきりと把握できていないため、指示が欲しい。
「HyperHES(イペレス)を点滴しろ!」
HyperHESとは我々が持っている点滴剤のなかで最も塩分が高い。深刻な出血多量のときに用いる。これが今必要なのだが、私はこの点滴剤をバックパックに携行していなかった。
出血の度合いや負傷の種類によって、用いる点滴剤が変わってくるため、我々医療班は3種類の点滴剤を使用するのだが、私はHyperHES以外の2種類を携行していた。
オアロ上級軍曹とバディーを組んだとき、彼がHyperHESを携行することになったのだ。我々2人に1つだけしか支給されなかった。フランス軍はHyperHESをあまり保有していないのだろう。
私は言った。「上級軍曹がHyperHESを持っています。」
「上級軍曹! HyperHESをくれ!」オアロ上級軍曹がこの場にいないことを知らないらしく、プルキエ少佐は声を張り上げた。
「了解!」
なんと私の後ろからオアロ上級軍曹の声が聞こえ、合流したばかりの上級軍曹が私の横に現れた。私は気づかなかったが、少佐には彼が駆けつけてくるのが見えていたのだ。
フォリエッジ・グリーンのキャメルバックBMFを背中から地面におろし、HyperHESの液体の入ったパックと点滴チューブを取り出し、準備にとりかかった。
負傷者の左前腕の内側においては、ミッサニがすでに誘導針付きカテーテルを静脈に刺しているところだ。右腕にはすでに2度刺しているので、今度は左腕だ。
カテーテルはスムーズに入っていく。カテーテルより少し上の静脈を指で押さえ、血流を抑えながら、誘導針を抜く。
上級軍曹が準備したばかりの点滴チューブの先端をミッサニに差し出す。先端までHyperHESが行き届いている。ミッサニは右手で受け取ると、親指でチューブ先端のキャップを外した。そして、そこを左腕のカテーテルに接続し、フィルムやテープで固定した。
そのあいだ、私にもちゃんと仕事はあった。
負傷者の喉に気管カニューレを縫い付けた少佐は、「アンビュバッグ」というラグビーボール型の風船のような、揉んで空気を送りこむ医療器具を取り出し、気管カニューレに接続した。
「ノダ、アンビュバッグを頼む。」
「はい、少佐殿。」
私は負傷者の左肩のそばにひざまずき、アンビュバッグを右手で揉み始めた。
衛生兵課程のときに習ったとおりの方法で、アンビュバッグを“シュー、シュー”と、親指先端と人差し指や中指が触れるくらいまで揉みきった。
「そうじゃない。こうするんだ。」
少佐が落ち着いた口調で言い、アンビュバッグに手を伸ばしてきたので、私は手を引いた。
アンビュバッグをつかんだ少佐は、“シュッ、シュッ、シュッ、シュッ”と、素早く小刻みに揉んだ。
「わかりました。」私は少佐に告げると、再びアンビュバッグを受け持ち、少佐の教えてくれた方法で揉み始めた。“シュッ、シュッ、シュッ、シュッ、シュッ、シュッ、シュッ、シュッ・・・・・”。
この瞬間から後方の医療班に負傷者を引き渡すまでの、私のノンストップな単純作業が始まった。単純だが、同僚1人の命が関わる重要な作業だ。責任を感じた。
少佐がこの揉み方について解説をする。私は揉みながら聴いた。
「肺に血が入り込んでいて、空気の入るスペースが小さくなっている可能性がある。空気をたくさん送りこむと、入りきらない空気が胃にまわり、嘔吐してしまうかもしれないから、こうするんだ。」
なるほど!軍医はすごい。私は負傷者の状態を考えず、教科書通りのやりかたでアンビュバッグを揉むくらいの頭脳しか持ち合わせていなかったが、少佐はしっかりと対応し、しかも、戦場で落ち着いて私にそうする理由を説明し、納得させた。
私がアンビュバッグを受け持ってからは、少佐はもっぱら、負傷者の状態を記す「フィールド・メディカル・カード」の記入と、我々に指示を出すほうに徹し、医療行為は我々3人で行なう形となった。演習で何回かやった状況だ。
頭を7.62mm弾で貫かれ、まぶたをパンパンに腫らし、鼻孔・口・喉の気管カニューレのところから小さな血の泡を立てて苦しむ本物の戦傷者が自分のすぐ目の前に横たわっているにも関わらず、演習をやっているような感じがする。
むしろ、演習のときより落ち着いている。演習のときは、我々が上手いこと対処できるかどうかを点検する係官が存在するが、実戦の場には存在しない。だいぶ気が楽だ。
点滴を設置した上級軍曹とミッサニは、近くにいた戦闘員に点滴剤のパックを高く保持するよう指示すると、負傷者の衣服を救急救命のハサミでジョキジョキと切りはじめた。
戦闘員が立った姿勢で、だらんと垂らした手に点滴パックを持って見守るなか、上級軍曹が上着を、ミッサニがズボンを切る。上着の袖は両方ともミッサニが点滴をするために早い段階で切っていた。戦闘服も下着もどんどん切られていき、負傷者は裸にされていく。頭部以外に負傷はないか確認するためだ。
「サバイバル・ブランケットを準備しろ。」少佐が指示を出した。
「持ってます。」私が引き受けた。
「ブリザード・サバイバル・ブランケット」という、日本のモンベル社と英国のマウンテン・イクイップメント社が共同開発した保温効果の高いサバイバル・ブランケットが、私のバックパックに入っている。
「しまった」と思った。バックパックが1.5mほど離れたところに置いてあり、手が届かない。この現場に合流し、気管切開キットを取り出したあと、そこに置いてそのままなのだ。アンビュバッグを止めたくないので取りにいけない。
すぐさま、そのバックパックの2mほど先から我々の活動を見ている戦闘員に言った。
「おいコワルスキー、そのバックパックをここに持ってきてくれ!」
コワルスキー一等兵は即座に対応してくれた。私は左手でアンビュバッグを操作しながら、右手でサバイバル・ブランケットを取り出した。ブランケットが圧縮密封され、硬く、レンガのような形になっている。20×10×5㎝くらいのサイズで、色は軍仕様の深緑だ。
「これを開けてくれ。」
そう言って私はブランケットの“レンガ”をコワルスキーに手渡し、開けるのを見守った。
厚いビニールの密封袋の隅には開けやすいように切れ目が入っているが、それでも開けにくかったため、コワルスキーはズボンの右ポケットから折り畳みナイフを引き抜き、親指で刃を出し、もともとあった切れ目よりも深い切れ目を入れ、緑色のレンガのような本体を取り出した。
「広げてくれ。」
コワルスキーはいっさい返事をしないまま、ナイフをポケットにしまうと、“レンガ”をほぐし、どんどん広げていく。外側が深緑で内側が銀色の素材が“チャリチャリ”と音を立てる。圧縮されていたシートは広がるとともに、2層構造になっているため空気を含み、膨らんだ。
(つづく)
(のだ・りき)