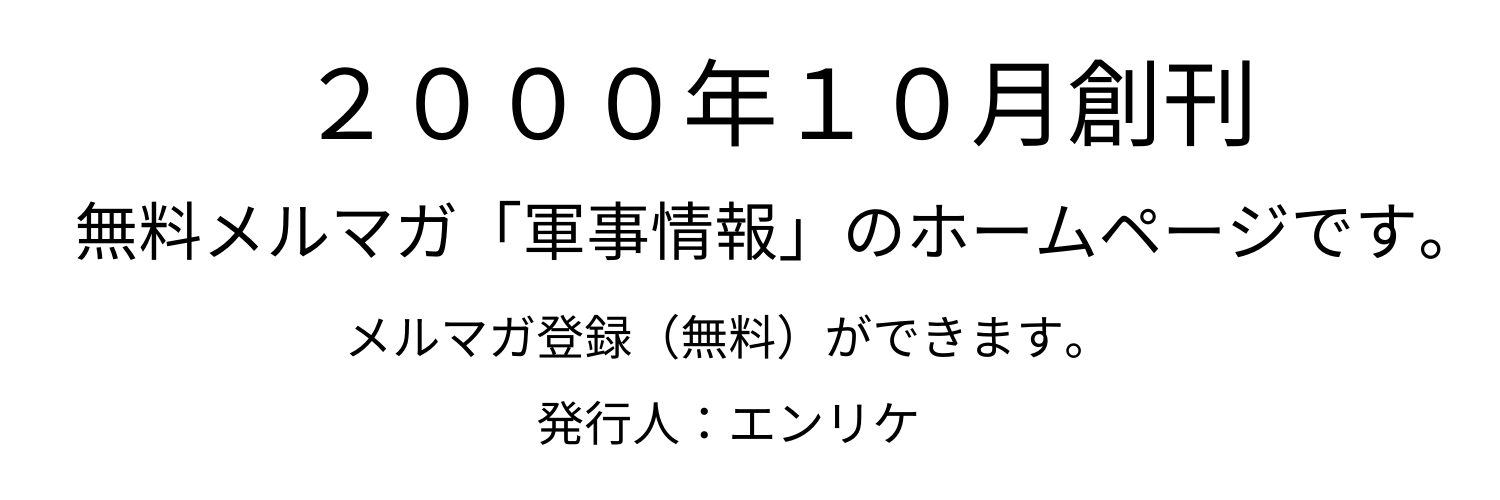戦争は人間的な営みである~新戦争文化論~(6) 「その暴力は平和の手段かもしれない」
From:石川明人
件名:その暴力は平和の手段かもしれない
2012年(平成24年)10月9日(火)
こんにちは。
石川明人(北海道大学助教)です。
コメントをいただきました。
Sさま。コメントありがとうございます。
おっしゃるとおり、平和とは戦争と戦争のあいだの一時期に他ならない、というのは確かにそのとおりかもしれません。戦争のスタイルは時代によって変化していくものですから、平和のうちにこそ、現在や未来の戦争スタイルを理解・予測することが重要だと思われます。平和を願い戦争を抑止したいならばなおさらのこと、戦争や軍事について勉強しておく必要があるのだと考えております。
黒猫ファンさま。コメントありがとうございます。
戦争死者数のカウントの仕方というのは意外と難しく、同じ戦争でも資料によって違うことが珍しくありません。「特攻による死」や「空襲による死」など具体的なケースの数字も、元の史料が十分でないことに加え、訓練中の事故死、行方不明者、戦後少したってから亡くなった方、などをどこまで「それが原因」の死だと数えるかという問題は複雑で、解釈や意見が人によって異なるようです。大東亜戦争による死者310万という数字がいつ頃から定着したのかは、申し訳ありませんが、詳しくは存じません。
では、【戦争は人間的な営みである】の第6回目をお送りいたしましょう。
今回のテーマは、「その暴力は平和の手段かもしれない」です。暴力はもちろん良くないものですが、その善悪の判断は、決して単純なものではありません。ここではテロリズムを例に考えてみたいと思います。
忌憚のないご意見、ご感想をいただければ幸甚に存じます。
(参考動画:石川明人「戦争は人間的な営みである」約15分)
http://www.youtube.com/watch?v=gL_de198QsE
************
▼メロスはテロリストか?
太宰治の『走れメロス』は、友情と信実の美しい物語である。しかし、主人公メロスは、ある意味では、テロリストになりかけた男だったとも言える。
この作品の冒頭は次の通りである。「メロスは激怒した。必ず、かの邪智暴虐の王を除かなければならぬと決意した」。メロスは妹の結婚式の準備のために、遠く離れた市を訪れる。だがそこにいる王が人々を殺害していることを知り、怒るのである。
メロスは言う。「呆れた王だ。生かして置けぬ」。そして彼は、買い物の荷物を背負ったまま、のそのそと王城に入っていった。だが、たちまち彼は巡邏の警吏に捕縛される。そして荷物や身体を調べられて、メロスの懐中から短剣が出て来たので、騒ぎが大きくなってしまったのである。
そして王の前に引き出されたメロスは、その短剣で何をするつもりだったのかと聞かれると、「市を暴君の手から救うのだ」と「悪びれずに」答える。その後のストーリーは周知のところであろう。学校の教科書にもこれが載っているのは、それが「信実」をテーマとした、健全な作品だと見なされているからである。
だが前半における物語の設定からすると、少なくとも体制側から見れば、メロスは危険なテロリストに他ならない。「生かして置けぬ」と言って短剣を持って王城に侵入すれば、何を意図していたかは明らかである。
一般市民が平和的な話し合いや正当な手続きをふむことなく、暴力で社会構造を修正しようとするならば、その者は現代ではテロリストと呼ばれるのである。
だが、太宰はメロスの人柄について、「邪悪に対しては、人一倍に敏感」な人物だと書いている。「単純な男」ではあっても、決して悪人ではない。むしろ純真無垢な善人なのだ。ほとんどの読者も、メロスを否定的に評価したりはしないであろう。だがそれは、結局のところ、私たちがみな、メロスの側に立ってこの物語を読むからに他ならない。
暴力、あるいは暴力の試みについての評価は、所詮は極めて主観的なものに過ぎない。誰がテロリストであるかという判断は、それを判断する人の立場や価値観によって異なるものである。「ある人にとってのテロリストは、別の誰かからすれば自由の戦士である」という言葉があるが、それはテロに関する問題の難しさを端的に表している。
仮面ライダーや、戦隊モノの特撮テレビドラマは、日本で何十年もの歴史をもつ人気シリーズであるが、これらはいずれも、武力によって悪を粉砕するのを「正義」とすることを基本線としている。しかし、暴力だけはいけません、話し合いで解決を、と口にする平和主義者の方たちも、子供たちにそれらを見せることには、特に大きな躊躇を感じてはいないように思われる。
戦争にしてもテロにしても、暴力や武力行使に対する評価は、見る者の立場によって異なる相対的なものでしかない。
「テロリズム」の定義は困難
一般に「テロリズム」と呼ばれる行為は、これまでさまざまな立場の人間によってなされてきた。右翼政党、左翼政党、国家主義組織、民族主義団体、宗教団体、革命家、政府など、その主体は実に多様である。
テロと呼ばれるものの多くに共通しているのは、個人や組織が自らの主張を宣伝し、相手に何らかの行為を強制するため、あるいは何らかの行為を中止させるために暴力行為をおこなう、あるいは暴力行為をおこなうぞと脅す、という点である。しかし、それでも「テロリズム」や「テロリスト」という概念の一般的な定義はなかなか困難である。
その理由は、まず第一に、テロリズムの「主体」およびテロ行為の「動機」が、あまりに多様だからである。そして第二に、ある行為がテロであるか否かは、それを判断する人の主観的立場によって異なってしまうものだからである。そして第三に、「テロ」をどう定義するかは、すなわち取り締まるべき対象を決定することにつながるため、結果として政治的な意図を強く反映してしまうからである。
とはいえ、さしあたり「テロリズム」の作業仮設的な概念規定として、次のようにまとめてもよいだろう。
すなわち、テロリズムとは、政治・宗教・民族・イデオロギーなど様々な動機から、社会のありようを矯正することを意図して、無差別的、非合法的に暴力を行使する、もしくは行使すると脅す行為である。その主体は、支配者側であることも被支配者側であることもあり、また個人あるいは国際的な組織である場合もあるが、いずれにしても、それが「テロリズム」であるかどうかは、それを判断する人の立場や価値観や時代によって異なる場合が多い。
最も広い意味での「テロリズム」は古代にまで遡ることができるが、その言葉の語源は、フランス革命の時代、ジャコバン党の恐怖政治体制にある。当時の「テロリズム」は、新体制を守るための統治手段と考えられており、いくぶん肯定的なニュアンスをもっていた。
今では「テロリズム」とは悪い行為だと認識されているが、当時はむしろ、高潔な生き方や民主的社会という理想と結びついたものでもあった。
一九四〇年代後半から五〇年代にかけて、アジア、アフリカ、中東などで、ヨーロッパ支配に対する、民族主義グループや反植民地主義グループの抵抗運動が起こり、それらにおける暴力をともなう反乱運動は「テロリズム」と呼ばれた。だが結果としては、イスラエル、ケニア、キプロス、アルジェリアといった国が独立できたのは、ある程度は、民族主義グループがおこなったテロ行為のおかげだと言えなくもない。
結局これまで、支配者側にとっても、被支配者側にとっても、テロリズムは良くも悪くも、政治目的達成のための有効な手段だったのである。
植民地国の弾圧や西洋の支配と戦う運動とそれにかかわる人々は「テロリスト」ではなく「自由の戦士」だと主張されることもしばしば見られる。
現在では、確かに「テロリズム」には完全にネガティブなイメージがもたれている。自らを「テロリスト」と名乗る人物や組織はまずない。しかし一九世紀のアナーキストたちは、自らを「テロリスト」であると公言し、その戦術は「テロリズム」であると率直に語っていたこともある。ブルース・ホフマンによれば、一九四〇年代の「レヒ」というユダヤ人武装組織が、自らを「テロリスト」と称した最後のグループの一つであるという。
現代においては、傍目にはテロ組織に見えるものも、彼ら自身は決して自らを「テロリスト」だとは言わない。彼らからすれば、むしろ現時点での社会や、政府や、経済などのシステムこそが、「真のテロリスト」なのである。それらが先に自分たちを迫害・攻撃しているのだから、彼らは自らや仲間たちを守らねばならない、というわけである。
アラブやイスラムの諸国は、パレスチナの反イスラエル・テロ闘争を、占領地からのパレスチナの「民族解放」という正当な目的をもつものだとして支持する。民族解放という目的は、手段としての武力行使を正当化するのであり、それはテロ行為ではなく、民族解放闘争という正しい、やむを得ない行為であると見なす。そしてそれを軍事力で圧殺しようとするイスラエルこそが国家テロ行為をしているとして非難する。
二〇〇一年の同時多発テロにおいても、一部の人たちは、あのテロをアメリカの覇権主義やグローバリズムに対するやむを得ない抵抗の手段として肯定するとともに、アメリカのアフガン攻撃を、一般市民をも巻き添えにする国家テロであると非難する。
結局のところ、いま私たちが使う「テロリスト」という言葉は、その人たちのなす行為への否定的な価値判断を含んだ呼称なのである。ある人や組織を「テロリスト」と呼ぶか否かは、その人や組織の主張に賛成するか反対するかという主観的な判断にかかっている。
「平和」と「反社会性」の基準
かつて「テロリスト」と見なされていた人が、後に時代が変われば「平和」に貢献した人物として評価されることもある。
例えば、かつてイギリス領パレスチナでは、ユダヤ人のテロ組織「イルグン」などが反英・反アラブ闘争をおこなっていた。一九四六年にイルグンは、イギリス支配の中枢となっていたエルサレムのキング・デヴィッド・ホテルを爆破し、九一名の死者と四五名の負傷者を出した。理由はもちろんそれだけではないが、結果として一九四八年にイスラエルが誕生している。
このイルグンの反イギリス・テロ闘争を指揮した人物が、後のイスラエル首相メナヘム・ベギンである。ベギンは一九七八年にエジプトと平和条約を締結し、ノーベル平和賞を受賞している。
また、ネルソン・マンデラも、一九六一年に「民族の槍」という武装組織の指導者となり、後に逮捕され、テロリストとして二八年間もの獄中生活をおくった人物である。だが周知の通り、マンデラは一九九三年にノーベル平和賞を授与され、その翌年には南アフリカ共和国の大統領にもなったのである。
このように、状況が変われば、かつて「テロリスト」とされた者も国家の指導者として尊敬され、ノーベル平和賞をもらう場合もある。自国の刑務所に入れられたり、あるいは軟禁・拘束されている状態でノーベル平和賞を受賞した人物としては、ドイツのカール・フォン・オシエツキー、ミャンマーのアウンサンスーチー、中国の劉暁波などもあげられる。
要するに、「平和」とか「反社会性」というのは、状況によって、時代によって、あるいはそれを見る人の立場によって、簡単に変わってしまうことも全く珍しくない。
テロリズムを必ずしも十把一絡げには批判すべきではないとし、それを弁護ないしは正当化しようとする議論もある。それは概ね次のようなものである。
まず、真の解放運動が政権側から「テロ行為」、「テロリスト」と非難されることは、歴史上幾度も繰り返されてきた。人々を奴隷におとしめた側は、それに抗議し抵抗する者たちをテロリストだとして批判するが、帝国主義、植民地主義、人種差別など、不当な搾取に対抗するには、ある種の暴力もやむを得ない場合があるという。
安易に「テロ」を非難することは、弱者ではなく強者の立場にたっているに過ぎないというわけである。問題なのは暴力そのものではなく、それを生む貧困、不平等、そして不満や絶望であり、基本的な人権、尊厳、自由、独立を主張し、外国支配に反対することを、一概に否定することはできないというのだ。
被害者側の立場からすれば、理由はなんであれ、暴力そのものを許すべきではないという意見も当然あるだろう。しかし、テロリストのような小さな組織や個人による暴力と、国家による暴力(正当な武力行使)とを明確に区別することもやはりできないはずである。
例えば、空港やショッピングモールのゴミ箱などに手製のパイプ爆弾をしかけて、半径一〇メートルの人々を無差別に殺傷するのと、正規軍のハイテク兵器が高度数千メートルから高性能爆弾を落として人々を殺傷するのと、本質的な違いはない。
理由や背景が何であれ、無差別に一般市民を攻撃することを「テロ」だというのならば、ロンドンを空爆したドイツ軍も、連合軍のドレスデン空爆も、アメリカ軍の東京空爆も、そして広島・長崎への原爆投下も「テロ」に他ならない。
そもそも、テロリストによる「不当な」暴力による死傷者よりも、国家による「正当な」武力行使による死傷者の方が、数の上でもはるかに多いではないか、という指摘もあるだろう。
あるテロリストは、戦争で数千人が殺し合うよりも、一機のハイジャックの方が効果がある、と言った。同じ暴力ならばどちらが被害が少なく「人道的」であるかと問われれば、私たちは言葉に詰まってしまうかもしれない。
しかし、こうした形でテロを正当化することはできないという主張もある。軍隊(正規軍)による戦闘にはまず宣戦布告があり、明文化された軍法や戦争法規があり、暴力を統制する意思があるが、テロリストにはそれらが無いという指摘である。
国家の正規軍がおこなう武力行使は、確かに暴力行為ではあるものの、そこには一応の規則、一般的な行動基準がある。
実際には、正規の軍隊も戦争法規のいくつかの項目に違反するということは少なくない。しかしそれらに違反することに対しては「戦争犯罪」という言葉がつかわれて非難され、罰せられることもある。
そうしたルールの遵守や司法的な賠償については、現在も決して完全で行き届いたものではないが、それが存在するかしないかの違いは無視できるものではない。それに対してテロリストは、そもそもそうした武力行使の原則や行動規範にしばられるつもりが全く無いように見える。
平和のための暴力?
テロリストと一般犯罪者の違いはどこにあるのだろうか。テロリストのおこなう暴力も確かに犯罪の一種だということもできるが、一般に「テロリスト」と通常の「犯罪者」はそれぞれ違ったイメージで捉えられているであろう。
両者の類似点としては、自らの目的のために暴力を用いる点や、無関係の一般市民を巻き込む点が挙げられる。相違点としては、一般犯罪者は個人的利益や満足のためにそれを行うのに対して、テロリストは社会的な影響力を意図するという点である。
また、テロリストは「大義」を自覚し、それを共有する人々から成る組織や協力体制をもつことがあるが、単なる犯罪者の場合はそのようなケースは稀である。そして、自らの行為を犯罪者は一応は「悪」だと認識している傾向が強いのに対して、テロリストは「善」だと強く信じている、という点が挙げられるであろう。この最後の点は、おそらくもっとも重要である。
テロリストは必ずしも邪悪で凶暴な人間ではない。文芸作品における登場人物の描かれ方として、ほとんどの読者はメロスの人格に特に不自然さを感じることはないだろう。それは、一般に純朴で優しく情に厚いという性格の持ち主でも、ある種の状況においては暴力も辞さない、ということに多くの人は違和感を感じないからである。
正義のためにはやむをえず暴力を用いざるをえない場合もあることを、誰もが多かれ少なかれ認めている。
しかしその一方で、確かに「テロリスト」には常識的な理屈が通じない、恐ろしい、狂信的な人々というイメージもある。だが、実際に様々なテロリストにインタビューをしてきた研究者やジャーナリストは、テロリストたちがいかに「普通」の人たちであって、むしろ彼らが温厚であったり、紳士的であったり、知的であったり、気さくであったりすることに驚くことが多いのである。
テロリストと極端な平和主義者には、似た傾向があるようにも思われる。それは、どちらも、良くも悪くも純粋さを求め過ぎている、という点である。
もちろん、清らかなもの、清らかで純粋な社会を求めることそれ自体は正しい。だが、浄化の思想は、しばしば排斥の思想につながるものである。人は、純粋さや清潔さを愛し、それを求めようとするあまり、相反するものを排除しようとし、結果として善意から悪をおこなってしまうことがある。そこまでいかなくても、異なる立場に対して、極めて不寛容になってしまうことがある。
そうした点では、極端な信仰の持ち主や、極端な右翼や、また極端な左翼は、実によく似ている。彼らはいずれも、極端な平和主義者なのである。
人間社会は、さまざまな思想や信念を持つ人たちと、複雑な利害関係との混沌から成っている。立場や考えはそれぞれ違う。しかしそれでも、皆が平和を求めていることだけは共通しているのである。
人間のありようについて、社会のありようについて、真剣に考えている人ほど明確な理想というものをもつ。そのこと自体は正しい。だが、そうした善意が逆に混乱を招かぬようにするには、むしろ現実の不完全さを受け入れる、ということも大切なのではないだろうか。
完璧な人間などいないように、完璧な社会もありえない。純粋な平和の実現のために思い詰め過ぎてしまったとき、人はテロリストにもなりえてしまう。テロも戦争も、それぞれの思い描く「平和」に自分や他人の生命をかけるという、奇妙な善意の営みである。
戦争が所詮は人間的な営みであるように、平和も所詮は人間的な希望である。平和を望む私たちと、戦争やテロを正当化する私たちは、同じ私たちである。
「戦争」には生命をかける価値などないと言うならば、「平和」にも生命をかける価値などない。生命をかけないぎりぎりで可能な限りの「平和」が、私たち人間に許されているレベルの「平和」なのではないだろうか。
真の平和主義に求められるのは、不完全な平和を受け入れる勇気と寛容さである。
社会の状況や人々の価値観や利害は常に変化しているのであって、そうしたなかで、純粋さから完全な理想を求め過ぎると、かえってひずみを招く。
私たち人間に可能な限りでの、適当な「平和」が何であるかを考えるべきであろう。要は、人間としての身の程を知る、ということである。
テロや戦争などをとおして、人間の本来的な弱さ、生真面目さ、そして暴力の正当性についての曖昧さを見ていくと、結局平和とは、究極的には、祈るものであって、拘るものではないようにも思われるのである。
(いしかわ・あきと)